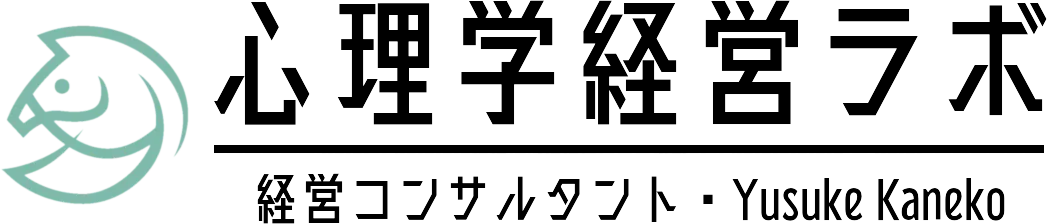中小企業が持続的に成長するためには、「今あるビジネスを強化すること(深化)」と「新しい市場や技術を開拓すること(探索)」の両方を、バランスよく進めることが求められます。
このような経営手法を「両利きの経営(Ambidexterity)」と呼び、ここ数年、多くの企業が注目しています。
しかし、大企業と比べ、中小企業はリソースが限られているため、両利きの経営を実現することは簡単ではありません。
効果的な施策を厳選し、そこに有効的にリソースを配分する必要があります。
そのためにも、何が中小企業の両利きの経営を決定づけるか知っておくことが大切です。
そこで今回は、経営学の研究をもとに、中小企業の両利きの経営を促進する重要な要因を分かりやすく解説します。
中小企業の「両利きの経営」に影響する8つの要因
複数の研究結果を統合し、中小企業の両利きの経営に、影響を与える要因を明らかにした、インド工科大学のルビナ・チャクマ助教らの研究があります。この研究には、8,422社分の中小企業のデータが含まれています。
これらのデータを分析したところ、以下の8つが、中小企業の両利きの経営の重要な要因であることが分かりました。
- ナレッジマネジメント:会社の中にある知識や情報を上手に集めて活用できる能力
- 起業家指向:新しいことに挑戦しようとする企業の姿勢
- 技術的能力:最新の技術を取り入れ、それを活用できる力
- 公式化:会社のルールや手続きがどれくらいしっかり決められているか
- 市場指向:顧客が求めているものを常に意識しているか
- ネットワーク能力:他の企業や団体と良い関係を築き、協力してビジネスを進める力
- 組織の状況:企業文化や職場環境
- 環境変動性:ビジネスを取り巻く環境の変化の激しさ(への対応力)
両利きの経営に最も影響を与えるのは「ナレッジマネジメント」
上記の8つの要因の中で、中小企業の両利きの経営に最も影響を与えるのは「ナレッジマネジメント」です。
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメント(英:knowledge management)とは、企業が持っている情報やノウハウを集め、整理し、活用することです。
企業の中には、過去の成功事例や失敗の経験、従業員が持っている専門知識など、さまざまな「価値ある情報」が存在しています。
しかし、それらが適切に共有されず、個人や部署ごとに埋もれてしまうと、同じような失敗を何度も繰り返したり、効率的に業務を進められなかったりします。
ナレッジマネジマントが上手くいっている企業は、社内で得た情報をデータベース化したり、会議や研修を通じてノウハウを共有したりすることで、「過去の知見を活かして、より良い意思決定を行う」ことができます。
例えば、新入社員が先輩社員の経験を学べる仕組みがあれば、業務をスムーズにこなせるようになり、会社全体の生産性も向上します。
ナレッジマネジメントが両利きの経営に強く影響する理由
ナレッジマネジメントが中小企業の両利きの経営に強く影響する理由は、過去の経験や蓄積された情報を活かしながら、新しい挑戦を同時に進めることができるからです。
両利きの経営では、現在のビジネスを効率よく運営する「深化(Exploitation)」と、新しい市場や技術を探求する「探索(Exploration)」の両方をバランスよく行うことが求められます。この2つを両立させるには、適切な知識の活用が不可欠なのです。
まず、適切なナレッジマネジマントができている企業は、社内で蓄積されたノウハウを活用し、業務の効率を向上させることができます。過去に成功したプロジェクトの手法や、効果的なマーケティング戦略をデータベース化しておけば、従業員はすぐに必要な情報を得ることができ、無駄な試行錯誤を減らすことができます。これにより、現在の事業をよりスムーズに深化させることができます。
一方で、新しいビジネスチャンスを見つけるためには、外部の情報や最新のトレンドを素早くキャッチし、それを社内で活用できる仕組みが必要です。ナレッジマネジマントの能力が高い企業は、業界の最新情報や競合企業の動向を継続的に収集し、それを社内で共有することで、新しい製品開発や市場参入のヒントを得ることができます。また、異なる部署間で知識を共有することでも、新しいアイデアが生まれやすくなります。
両利きの経営のためのナレッジマネジメントの実践
ナレッジマネジメントは、大規模な予算や人員を掛けなくとも、行えるものが多いです。そういった点からも、中小企業が両利きの経営を実践するためには、ナレッジマネジメントから取り組むのが良いといえます。
具体的には以下のような方法があります。
1.社内ナレッジ(知識)の可視化とデータベース化
企業内に蓄積された知識やノウハウが個人や特定の部署に留まってしまうと、組織全体での活用が難しくなります。そのため、過去の成功事例や失敗事例、業務マニュアル、研修資料などをデータベース化し、誰でもアクセスできる仕組みを整えることが有効です。
例えば、クラウドや社内Wikiを活用し、プロジェクトごとの学びを記録することで、新しい事業や業務改善に活かせます。特に、異なる部署間での知識共有を促進することで、活用と探索の両方を支援する環境が整います。
2.知識共有の文化を育成する
単にデータベースを作るだけではなく、従業員同士が知識を共有しやすい企業文化を育てることも重要です。そのためには、定期的な勉強会や知識を共有する機会を増やし、従業員が自らの知識や経験を発表する場を設けると効果的です。
また、社内SNSやチャットツールを活用し、気軽にアイデアや情報を交換できる仕組みを作ることも有効です。例えば、成功したマーケティング手法や顧客対応の工夫を共有することで、他の部門でも同様の取り組みを展開しやすくなります。
3.外部の知識を積極的に取り入れる
中小企業が限られたリソースの中で競争力を維持するためには、社内の知識だけでなく、外部の最新情報を積極的に取り入れることも不可欠です。
業界のセミナーや勉強会に参加し、新しい技術や市場動向を学ぶことが重要です。また、大学や研究機関、他企業とのネットワークを強化し、外部の専門家やパートナー企業からの知見を活用することも効果的です。特に、新規事業の探索には、異業種のアイデアや海外市場の情報が役立つことが多いため、積極的に外部と連携することも有効です。
4.知識を活用した試行錯誤の促進
新しいアイデアの実践や、試行錯誤を積極的に行う文化を育むことも必要です。例えば、社内で「スモールテスト」の仕組みを導入し、小規模なプロジェクトとして新しいアイデアを試す機会を増やすことが効果的です。
このような仕組みを整えることで、過去の知識を活かしつつ、新しい事業の探索にもつなげることができます。特に、失敗を学びとして活用する仕組みを作ることが、両利きの経営の成功には不可欠です。
経営層が「知識の価値」を理解することが大事
ナレッジマネジマントを活用した両利きの経営は、中小企業の成長と競争力向上に大きく貢献します。その実践には経営者の意識改革も重要な要素となります。
どれだけ優れたナレッジマネジマントの仕組みを整えても、経営層が知識の価値を理解し、活用を促進しなければ、現場の従業員は積極的に参加しにくくなります。
経営者自身が率先して学び続け、知識の共有を奨励する文化を築くことで、組織全体が知識を活用する土壌を育むことができます。
また、ナレッジマネジマント能力を向上させるためには、従業員の学習意欲を高める工夫も欠かせません。例えば、優れた知識の活用や共有を行った社員を表彰する制度を設けることで、従業員のモチベーションを高めることができます。
さらに、知識の蓄積を負担に感じさせないよう、シンプルで使いやすいツールを選ぶことも大切です。情報共有の負担が少なければ、自然と知識が蓄積され、組織全体での活用が促進されます。
小さな取り組みを積み重ね、日々の業務の中で少しずつ知識を蓄積し活用することで、企業は確実に強くなります。
変化の激しい時代において、「知識を資産として活かすこと」が、限られたリソースの中で最大限の成果を生み出すカギとなるのです。中小企業こそ、知識管理の重要性を理解し、それを成長の原動力として活用していくことが求められています。
参考文献:Rubina Chakma and Sanjay Dhir. (2023). Exploring the determinants of ambidexterity in the context of Small and Medium Enterprises (SMEs): A meta-analytical review.