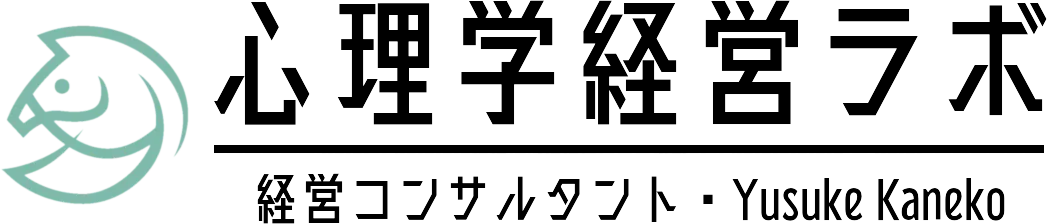Netflixが今や無敵の存在として世界中で利用されているのは、単にIT技術の進化や動画配信という仕組みを取り入れたからではありません。
本当の理由は、既存の競争市場で戦うのではなく、全く新しい市場を自ら作り出したことにあります。
競争相手が存在しない場所で独自の価値を提供することで、他社が簡単には追いつけない地位を築き上げたのです。
今回は、Netflixがどのようにして唯一無二の存在となったのか、「ブルーオーシャン戦略」の視点から解説します。
競争しない企業こそ最強–ブルーオーシャン戦略とは
ほとんどの企業は、同じ業界内でライバルと激しくシェアを奪い合っています。より安く、より早く、より高品質な商品やサービスを提供しようと必死です。
しかし、こうした競争の激しい市場では、価格競争に巻き込まれ、どれだけ頑張っても利益率が下がってしまいます。
ブルーオーシャン戦略は、このような既存市場、いわゆる「レッドオーシャン」で戦うのではなく、競争そのものが存在しない新しい市場、つまり「ブルーオーシャン」を生み出すという考え方です。
例えば、これまで誰も注目していなかった顧客層に目を向けることや、既存商品とはまったく違う切り口でサービスを提供することによって、他社と競う必要のない独自市場を作り出します。
ここで重要なのは、差別化と低コスト化を同時に実現することです。普通は、差別化すればコストが上がり、コストを下げれば差別化ができなくなると考えがちです。
しかしブルーオーシャン戦略では、これらを両立させ、顧客にとってまったく新しい価値を提供します。
つまり、競争に勝とうとするのではなく、競争を無意味なものにする。これがブルーオーシャン戦略の本質なのです。
【関連】「ポーターの3つの基本戦略」の中で最も業績に影響を与えるのはどれか?
Netflixが切り開いた「競争のない市場」
Netflixはもともと、インターネットを使ったDVDの郵送レンタルサービスとしてスタートしました。
店舗に足を運ばなくても、自宅で好きな映画を選び、郵送で受け取り、見終わったらポストに返却するだけという仕組みは、当時の消費者にとって革新的でした。この時点でも、レンタルショップという既存のビジネスモデルへの挑戦といえます。
しかし、Netflixが真に無敵の存在となったきっかけは、DVDレンタルからストリーミング配信へ全面移行したことです。
オンラインで映画やドラマを直接配信するこの仕組みによって、視聴者はレンタルショップへ行く必要がなくなりました。貸出中で借りられないという問題もなくなり、返却期限や延滞料金といった煩わしさも消えました。
さらに、インターネット環境さえあれば、パソコンやスマートフォン、タブレットなど、どのデバイスでもいつでもどこでも作品を楽しめるようになりました。
ソファに座っていても、通勤電車の中でも、好きなときに好きなコンテンツを選んで視聴できる。これまで「映画を見るためには店で借りる」という常識が当たり前だった人々にとって、この変化は衝撃的でした。
Netflixは、ユーザーの行動そのものを変え、旧来型のレンタルという選択肢を過去のものにしたのです。
4つのアクションで読み解くNetflixのブルーオーシャン戦略
Netflixがなぜここまで成長できたのかを理解するためには、ブルーオーシャン戦略で提唱されている「Four Action Framework(4つのアクション)」という考え方が役立ちます。これは、ビジネスモデルを見直すときに重要な4つの問いを提示するものです。
【1】Eliminate(排除)
Netflixは、従来のレンタルビデオ業界で当たり前だった仕組みを思い切って取り除きました。たとえば、店舗に行って借りる手間、在庫がないことで借りられない不便さ、返却期限によるストレス、延滞料金の支払いなどです。これらはすべて、利用者にとって大きな不満であるだけでなく、企業側にとっても在庫管理や延滞回収のコスト負担となっていました。Netflixはこの仕組みそのものを不要にしました。
【2】Reduce(削減)
DVDを物理的に取り扱う必要がないことで、物流費や店舗運営費、在庫管理費といったコストを大幅に減らしました。レンタル店舗では店舗家賃やスタッフ人件費、棚卸しなど多くの固定費がかかりますが、ストリーミングに切り替えることで、こうしたコスト構造を根本から変えました。
【3】Raise(向上)
Netflixは、ただコストを削減するだけではなく、利用者体験の質も向上させました。作品数を豊富に揃えただけでなく、誰が見ても迷わない直感的な操作画面や、過去の視聴履歴から好みを分析する推薦アルゴリズムを提供しました。これにより、ユーザーは探す手間なく、自分が見たいと思える作品に出会えるようになりました。
【4】Create(創造)
そして何よりも大きな価値は、いつでもどこでも好きなときに作品を楽しめるというオンデマンド配信という新しい視聴スタイルを生み出したことです。これにより、消費者は「お店で借りる」から「いつでも観られる」へと行動パターンを変えることができました。この変化が、Netflixを単なるレンタル代替サービスから、生活インフラのような存在へと押し上げたのです。
Netflixが築いた競争優位の構造
Netflixがここまで成功を収めたのは、他社より少し便利で安いサービスを提供したからではありません。ライバルと比べてどれだけ優れているかを競うのではなく、そもそも比べられる相手がいない市場を自ら作り出したことが最大のポイントです。
多くの企業は、より安い価格で、より高い品質を、より早く提供することで差別化しようとします。しかし、このやり方では、結局同じ土俵で戦うことになり、いつかは価格競争に巻き込まれてしまいます。Netflixはこの常識を覆し、「ライバルが存在しない市場」で独自の価値を提供することに集中しました。
ストリーミングという新しい視聴方法を広げることで、既存のレンタルショップやテレビ放送とは全く異なる体験を生み出しました。このおかげで、価格や品揃えで競う必要がなくなり、安定した収益を確保できるようになったのです。
さらに、Netflixは映画やドラマを配信するだけでは終わりませんでした。利用すればするほど好みに合った作品を薦めてくれるレコメンド機能や、Netflixでしか観られないオリジナルコンテンツを次々に生み出しました。
これらの仕組みにより、ユーザーは他社サービスへ乗り換える理由を失い、Netflixから離れにくくなっていきました。
つまりNetflixは、ユーザーにとっての「唯一無二の選択肢」となり、競争相手と比較されることなく、自社のサービスを使い続けてもらえる強固な競争優位性を築いたのです。
ブルーオーシャン戦略の落とし穴
ブルーオーシャン戦略には、いくつかの落とし穴もあります。
まず、新しい市場を切り開くためには、多額の投資が必要です。既存のビジネスモデルを捨てる覚悟も求められます。
NetflixがDVDレンタルからストリーミング配信へと事業の中心を移したときも、大きなリスクを背負っていました。もしもインターネット環境の整備が遅れていたり、ユーザーがストリーミングに慣れることができなかったら、今のような成功はなかったでしょう。
さらに、ブルーオーシャン戦略で成功すると、その市場の魅力に気づいた他社が必ず参入してきます。
当初、Netflixはストリーミング市場で独占的な立場にいましたが、今ではDisney+、Amazon Prime Video、HBO Maxなど強力な競合が次々と登場しています。かつて誰もいなかった市場は、いつしか激しい競争の舞台(レッドオーシャン)へと変わっていきました。
このように、一度ブルーオーシャンを築いても、それを守り続けるのは簡単ではありません。市場がレッドオーシャン化する前に、次のブルーオーシャンを探し続ける必要があります。
Netflixも現在、インタラクティブ作品やゲーム配信事業に取り組むなど、新たな成長の柱を模索しています。
過去の成功体験にとどまらず、変化を恐れず挑戦を続ける姿勢こそが、ブルーオーシャン戦略を持続させるために必要なのです。
Netflixが示したブルーオーシャン戦略の本質
Netflixの成長の軌跡を振り返ると、彼らが行ったのは単に競合他社に勝つための戦略ではなかったことが分かります。
競争の舞台から降り、まったく新しい市場を生み出したことで、他社が追いつけない圧倒的な立場を築き上げたのです。
競争に勝つことを目標にすると、価格競争や機能競争に陥り、やがて疲弊します。しかしNetflixは、競争相手が存在しない場所を選び、新たな顧客体験と価値を作り出しました。これが、ブルーオーシャン戦略の本質です。
経営者にとって重要なのは、自社がいま置かれている市場でどう戦うかだけではありません。その市場自体を変えることができるか、新たな需要を創り出せるかを再考することです。
競争から抜け出して自分たちだけの市場を築けたとき、企業は初めて無敵になるのです。
これからの10年を生き抜くためには、既存市場を守るだけでは不十分です。競争という枠組みを超え、まだ誰も踏み込んでいない市場を見つけ出し、そこで新たな価値を生み出す挑戦こそが、企業の未来を切り開くのです。
参考文献:Mukhlis Yunus. (2021). A Review On Blue Ocean Strategy Effect On Competitive Advantage And Firm Performance.