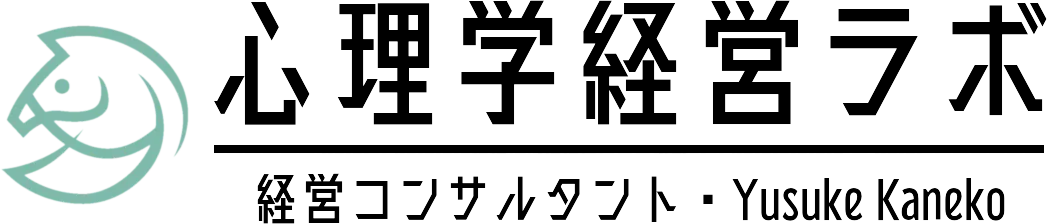ビジネスの世界では長年、「競合他社とは戦うもの」「協力するなら非競合と」という考え方が一般的でした。
しかし、時代の変化とともに、企業の間に生まれてきたのが「コーペティション」という新しい関係性です。
これは「協力しながら競争する」という柔軟な戦略です。
実際、テクノロジー業界や航空業界、自動車産業などさまざまな分野で、競合同士が一部で手を組み、別の部分では激しく争っているケースが見られます。
では、このコーペティションという戦略は、本当にうまくいくのでしょうか?
そして、どのような状況で成功し、どんな場合に失敗するのでしょうか?
今回は、実証研究をもとに、コーペティション戦略の効果と、それが成功するための条件を分かりやすく解説していきます。
コーペティションとは
コーペティション(Coopetition)とは、「Cooperation(協力)」と「Competition(競争)」を組み合わせた言葉で、競合する企業同士が一部で協力しながら、同時に他の部分では競い合う関係のことです。
つまり、「ライバルなのに手を組む」という、矛盾しているようで実は戦略的な関係です。
コーペティションは次のような場面で見られます。
- スマートフォン業界:液晶技術を共同開発しながら、完成した製品では市場で競争している。
- 航空業界:複数の航空会社がコードシェアや共同便で協力しつつ、価格やサービスでは顧客を奪い合っている。
- 自動車業界:共通の部品やプラットフォームを開発するために協力しながら、それぞれのブランドで異なる戦略を展開。
このように、コーペティションは「敵か味方か」ではなく、「協力するところは協力し、競うところは競う」という柔軟なパートナーシップを意味します。
200社以上のコーペティションを分析
コーペティションの効果を測定した、ラッペーンランタ・ラハティ工科大学のパーヴォ・リタラ教授の研究があります。
この研究では、「競合同士が協力すると、本当にうまくいくのか?」を調べるために、実際の会社のデータ(209社分)を分析しています
特に、コーペティションによって、どのくらい新しい商品やサービスを生み出せるか(イノベーション)、そして売上や利益がどれくらい伸びるかに注目しています。
研究の対象となったのは、100人以上の社員がいて、日頃からR&D(研究開発)や新サービスの展開を積極的に行っている会社です。
これらの会社の経営者やR&D担当者から、コーペティションによって、どのような成果を得られたかを確認しています。
さらに、「コーペティションの成功には環境条件も関係する」という仮説のもと次のポイントも確認しています。
- 市場の不確実性:顧客のニーズや流行が変わりやすいかどうか
- ネットワーク外部性:その商品を使う人が多いほど、商品価値が上がるタイプかどうか(例:SNSやスマホなど)
- 競争の激しさ:同じような商品を出している会社がどれくらいあるか
コーペティションが成功する条件
分析の結果、コーペティションは条件次第で、成功することもあれば、失敗することもあることが分かりました。
では、どのような条件のときにうまくいくのでしょうか?
それは以下の通りです。
成功条件①:市場の変化が激しいとき
市場の変化が激しく、先行きが不透明な状況では、企業は大きなリスクを抱えながらビジネスを展開しなければなりません。
ある技術が来年には時代遅れになってしまう、顧客のニーズが急に変わる、新しい競合が突然現れる──このような不確実な状況は、特にハイテク業界やスタートアップ界隈でよく見られます。
このような「市場不確実性」が高い環境では、1社だけで先の読めない世界に挑むよりも、競合と手を組んでリスクやコストを分担したほうが有利になります。
競合企業は、業界内で似たような課題や関心を持っているため、「何が懸案事項か」「どこにチャンスがあるか」をお互いによく理解しています。そのため、一緒に動くことでより迅速かつ柔軟に、新市場の開拓や新製品の開発ができるのです。
たとえば、ある新技術が世の中に広まりそうだとします。単独ではリスクが大きすぎて手が出せない場合でも、ライバル企業と一緒に取り組むことで、「やってみよう」という決断がしやすくなります。結果として、挑戦のスピードが速くなり、変化への対応力も高まるのです。
成功条件②:ネットワーク外部性があるとき
ネットワーク外部性とは、「ユーザーが増えれば増えるほど、その商品やサービスの価値が高まる」という特徴のことです。
例として分かりやすいのがSNSやスマホ、決済アプリなどです。たとえば、自分しか使っていないSNSはほとんど意味がありませんが、多くの友人が使っていればいるほど便利になります。
こういった分野では、競合同士が協力して、製品やサービスの互換性や共通の規格を整えることが、市場全体にとってメリットになります。なぜなら、ユーザーは「どの製品でも同じように使えること」を求めるからです。
携帯電話の通信規格やスマートフォンの充電端子などが統一されているのは、企業が協力してルールを決めた結果です。これにより、消費者は機種を変えても使いやすく、企業もより大きな市場で競争できるようになるのです。
つまり、ネットワーク外部性がある製品・サービスでは、コーペティションによって、市場全体の価値が上がり、その中で自社も利益を得られるという「Win-Win」の関係が生まれやすくなるのです。
成功条件③:競争がそこまで激しくないとき
一般的には、競争が激しい業界ほど工夫が必要だと考えられますが、この研究では、競争があまり激しくない業界のほうがコーペティションが成功しやすいという結果が出ています。
その理由のひとつは、ライバル企業の数が少ないため、お互いに警戒せず、信頼関係を築きやすいことです。敵対心よりも、「一緒に市場を育てよう」「お互いに得する協力をしよう」という考え方が生まれやすくなるのです。
また、競争がそれほど激しくない分、限られたリソースを無駄なく使いながら、共通の課題に集中できるというメリットもあります。たとえば、ニッチな市場で似た技術を開発している企業同士が手を組むことで、少ない予算でも成果を出せる可能性が高まります。
つまり、ライバルが少なく、対立よりも協調がしやすい環境では、コーペティションはよりスムーズに機能するということです。
コーペティションが失敗しやすい条件
一方で、競争が激しすぎる環境では、コーペティションがうまくいき難いことが、今回の研究で明らかになっています。
競合企業があまりに多い市場では、すべてのライバル企業と協力関係を築くこと自体が非現実的です。
企業の経営資源(人材、時間、資金)には限りがあります。仮に複数の競合相手と同時にアライアンスを結ぼうとすれば、それだけで組織の負担は大きくなり、結果的に中途半端な連携に終わってしまう可能性が高くなります。
また、協力関係においては、少なからず重要な情報や技術、ノウハウを共有する場面が出てきます。たとえば共同で製品開発を行う場合、製造プロセスの細部やマーケティング戦略を共有することが避けられません。
しかし、競争が激しい環境では、情報が他の競合に漏れるリスクが格段に高まります。特に、コーペティションの相手が他の競合企業とも密接な関係を持っている場合、意図せず自社の強みが他社に伝わってしまうことも考えられます。
さらに、コーペティションの本質は「協力しながら競争すること」ですが、競争が過熱しすぎていると、協力部分が成り立たなくなる危険性があります。
つまり、表向きは協業しているように見えても、裏では激しい情報戦や市場争いが続いており、信頼関係が崩れやすいのです。こうした状態では、協力から得られるはずの利益よりも、信頼を失うコストや損失の方が大きくなってしまうのです。
自社の企業文化や組織内の意識も重要なポイント
コーペティションは、従来の「協力か競争か」という二者択一の発想を超えた、現代の複雑なビジネス環境に適した戦略といえます。
しかし、実際にこの戦略を活用する際には、企業文化や組織内の意識も大きな影響を与えることが分かっています。
たとえば、社内に「競合は敵である」という考えが根強く残っている企業では、いくら外部環境が整っていても協力関係が機能しない可能性があります。
つまり、コーペティションを成功させるためには、外部環境の見極めだけでなく、内部の信頼構築やマインドセットの変革も同時に求められるのです。
協力する相手を見極める目、共有する情報の線引き、そして協業によって何を達成したいのかという目的意識。これらを社内で共有し、同じ方向を向くことが、コーペティションを「戦略」として機能させるための鍵となります。
参考文献:Paavo Ritala. (2012). Coopetition Strategy – When is itSuccessful? Empirical Evidence onInnovation and Market Performance.