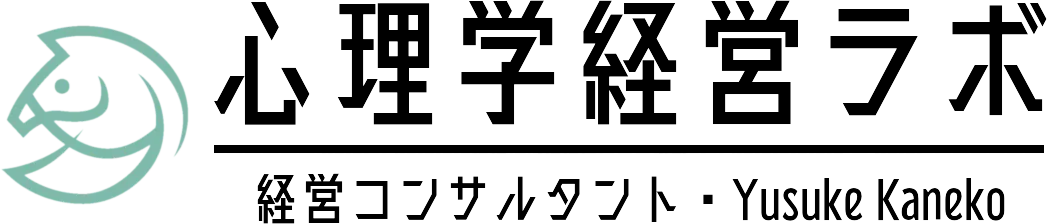産業構造の変化や技術革新の影響で市場が縮小し、事業の継続が難しくなっている中小企業も数多く存在します。
たとえば、印刷業やレンタルビデオ店などは、かつて生活に欠かせないサービスでしたが、デジタル化によって需要が急激に減ってしまいました。
こうした業界では、価格競争が激しくなり、投資に回す余裕もなく、倒産や廃業に追い込まれる企業も少なくありません。
とはいえ、このような「衰退産業」にいる中小企業の中にも、しぶとく生き残り、成長を続けている企業も存在します。
彼らはなぜ生き残れたのでしょうか、他の企業と何が違ったのでしょうか。
衰退産業でも成長する中小企業が採用している3つの戦略
クイーンズランド工科大学のギャレス・トーマス博士らがオーストラリアの印刷関連の中小企業を対象に行った調査があります。
オーストラリアにおいても、印刷業は衰退産業とされており、多くの企業が不振にあえいでいますが、そんな中でも一部の企業は成長を続けています。
そのような成長企業14社の経営者や幹部から長時間に渡りインタビューを行い、衰退産業でも生き残る企業にどんな共通点があるのか、検証したのがこの調査です。
検証の結果、以下の3つの共通点が浮かび上がりました。
1.外部ネットワークの再構築
成功している中小企業の最も大きな特徴のひとつは、外部との関係を柔軟に再構築している点です。
印刷業のような衰退産業においては、もともとの取引先や協力先の多くも同じように、困難に直面しています。そうした中では、業界内で助け合うだけでは限界があります。
成功企業はこのような状況を打開するために、異業種との連携を積極的に進めていました。
ある企業は、従来の出版業や事務印刷といった狭い市場から離れ、小売業やイベント業界と連携することで、販促用ディスプレイや装飾印刷といった新しい需要を開拓しています。
オンライン化の波を受けて変化を迫られている小売店は、店頭で目を引く物理的な販促物の必要性が高まっており、そこに印刷技術が応用できたのです。
また、これまでのように新しい機械を購入して最新技術を取り入れるだけでは不十分であることも明らかになっています。それよりも、顧客の業務プロセスに深く入り込む形での関係構築が重視されていました。
顧客の注文システムと自社の工程を連動させたり、注文から納品までを一体化した仕組みを整えることで、顧客にとって「代替の効かない存在」としての立ち位置を築いていたのです。
こうした外部との新たなつながり方が、企業の生存を支える重要な要素となっていました。
2.無形資産の活用
印刷業は長年、機械設備や技術力といった「有形資産」が重要視されてきました。
しかし、今回のインタビュー調査では、「無形資産」、つまり人材のスキルや柔軟性、企業文化や知識の蓄積が、企業の競争力を大きく左右していることが示されています。
成功している企業では、社員が一つの仕事に特化するのではなく、複数の作業を横断的に担当できるよう教育されています。
たとえば、印刷機の操作だけでなく、加工や発送までを一人の社員が対応できるようになっており、急な欠員にも柔軟に対応できる体制が整っているのです。
この「多能工化」は、生産性の向上だけでなく、新しいことへのチャレンジを可能にする文化づくりにもつながっています。
社員の創造力を刺激するための工夫も見られました。
ある企業では、社員が週末に職場の設備を自由に使えるようにし、個人のプロジェクトを通じて新しい技術や素材に挑戦できる環境を整えていました。
そうした「遊び」の中から新しい商品アイデアが生まれ、事業化につながった事例も報告されています。
3.損益のバランス(両利きの経営)
企業が存続するためには、今ある収益を守ることと、新しい収益源を開拓することの両立が求められます。いわゆる「両利きの経営」です。
特に、縮小している市場の中で生き残るためには、リスクを取りすぎず、かといって守りに入りすぎない「バランス感覚」が重要になります。
衰退産業の中でも、うまくいっている企業は、既存の顧客に対しては効率よくサービスを提供する一方で、新しい市場や製品の開発にも同時に取り組んでいることが確認されました。
たとえば、従来の大量印刷に関しては、できるだけコストを抑えつつ安定的に売上を確保しながら、それと並行して、少量でも高付加価値のある特殊な印刷物を新たに開発・提供していくという戦略が取られていました。
前者は低い利益率ながら継続的な収益源となり、後者は試行錯誤が必要で不安定な部分もありますが、成功すれば高い利益をもたらす可能性があります。
この二面性のある戦略を採用することによって、安定性と成長性の両方を確保していたのです。
また、新しい商品やサービスを開発するだけでなく、それを既存顧客に組み込む形で提供することで、新規顧客の獲得コストも抑えられていました。
【関連】中小企業が大手企業に勝つためにアピールするべきキーワードとは?
付き合う顧客の性質も重要
以上のように、外部ネットワークの再構築、無形資産の活用、損益のバランスという3点が、衰退産業でも成長する多くの中小企業に共通する戦略でした。
それに加えて、取引相手となる顧客の性質も、組織の変化や学習に大きな影響を与えることも分かっています。
特に、変化を恐れず新しい取り組みに挑戦する「革新的な顧客」との関係が、企業内部の成長を促す重要な要因となります。
こうした顧客は、従来の仕様や枠組みにとらわれず、今までにない製品やサービスの開発を企業に求める傾向があります。
その結果、企業側は通常の業務とは異なる課題や要望に向き合うことになります。それを解決するために、従来使っていなかった素材や加工方法を試すなかで、新しいサービスラインへと発展することもあります。
また、試作品の段階から顧客が意見を出し、企業とともに改善を重ねていくという協働型のプロセスも多く見られます。このような関係性では、顧客が単なる「発注者」にとどまらず、開発パートナーのような存在となり、企業内での試行錯誤や技術的な応用力が高まっていきます。
さらに、革新的な顧客の要望に対応する過程で、社員自身が新しいスキルや知識を獲得することも少なくありません。
未知の課題に向き合うことで、個人やチームが新たな経験を積み、それが組織全体の学習力の向上につながっていきます。このように、顧客とのやり取りが単なる取引を超えて、企業の進化を促す契機となるのです。
つまり、外部からの刺激を受け入れ、積極的に対応する姿勢を持つことが、衰退産業における中小企業にとっては、重要な成長要素であるといえます。
企業がどのような顧客と関係を築くかという視点も、戦略の一部として意識する必要があります。
参考文献:Gareth H. Thomas, Evan J. Douglas. (2021). Small Firm Survival and Growth Strategies in a Disrupted Declining Industry.