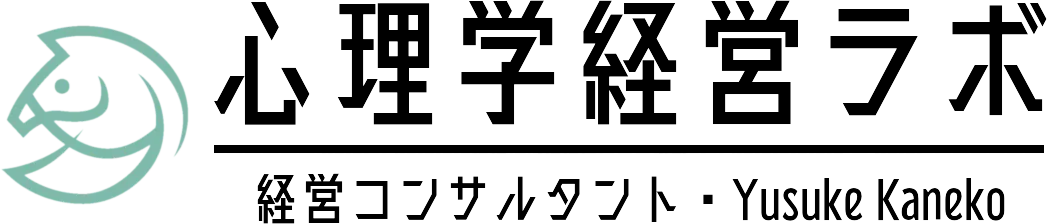実店舗でも、ネットショップでも、購買率を高めるためには、価格を見せるタイミングに気をつける必要があります。
なぜなら、価格を先に見せるか、商品を先に見せるかによって、消費者の判断は変わるからです。
価格を先に見せると、消費者は「その金額に見合う価値はあるか?」という基準で判断します。
商品を先に見せると、直感的な「好き」「欲しい」という感情で判断します。
これは神経科学の実験によって、証明されていることです。
そして、どちらのパターンがより購買率を高めるかは、その商品の特性によって変わります。
消費者の購買判断時の脳で測定
商品を購入する場面を想定した、ハーバード・ビジネススクールのウマ・カルマルカル助教らの実験があります。
この実験の被験者は、脳を測定するための、MRI装置の中に入れられ、そこで画面に表示される商品と価格を見て、購入するかどうかを選択しました。
商品の提示方法には二つのパターンがありました。
一つは、最初に商品を見せてから価格を提示する「商品先行」パターン、もう一つは、価格を先に提示してから商品を見せる「価格先行」パターンです。
すべての被験者は、両方のパターンで購買判断を行い、脳の活動を測定されました。
価格を先に見ると感情に流された判断をしなくなる
この実験の結果、商品を先に見た場合(商品先行)と、価格を先に見た場合(価格先行)とでは、購買の意思決定プロセスに違いが生じることが分かりました。
「商品先行」の場合、脳内の「報酬系」と呼ばれる、側坐核の活動が活発になりました。ここは、好き嫌い等の感情的な判断に関連する領域です。
つまり、商品先行の条件では、商品が魅力的かどうかを基準に判断し、魅力があると思えば、購買意欲が高まるということです。感情に流された判断をしやすくなるともいえます。
一方で、「価格先行」の場合、脳内の内側前頭前野の活動が活発になりました。ここは、価値の評価や合理的な判断を行う領域です。
直感的な「欲しさ」で評価せず、「価格と価値のバランス」に基づいた評価を行うようになったということです。
単なる「欲しい」という感情に流されにくくなったともいえます。
実用性の高い商品は価格先行のほうが購買率が高まる
一般に、消費者が感情に流されやすい状態になってくれたほうが、冷静な判断力が失われ、商品は売れやすくなるものです。
なので、価格は後から見せたほうが良いと、言えそうですが、必ずしもそうではありません。
実は今回の実験では、別の被験者を対象に、先ほどと同じように、商品先行条件と価格先行条件で、複数の商品を見せ、購買意欲を確認しました。
そのデータを分析したところ、浄水ポットやUSBメモリ、乾電池といった「実用性の高い商品」では、価格先行の方が、購買意欲が高まりやすいことが分かりました。
機能的な価値が分かりやすい商品では、消費者に「価格に見合う価値があるか?」と冷静に判断してもらったほうが、よりその価値を理解してもらいやすいからと考えられます。
店舗とネットショップの戦略
今回の実験では嗜好品の購買率は検証されていませんが、先行研究の知見などから考えると、嗜好品では商品先行が有利になる可能性が高いです。
言い方は悪いですが、商品自体の価値が曖昧なものは、冷静に判断されるより、感情的に判断してもらったほうが売れるのです。ブランド品を買う時に、「その金額を払うだけの機能的価値があるか?」と判断されたら売れません。
以上を踏まえると、実店舗やネットショップでは、次のような工夫が求められます。
1.店舗でのディスプレイ
ブランドの世界観を重視する商品の場合、価格情報を前面に出しすぎると、その魅力が薄れてしまう可能性があります。
高級品を扱う店舗では、価格タグをすぐに見えないように工夫し、まずは商品のデザインや品質をじっくりと体験してもらうことで、感情的な価値を高める演出が可能となります。
一方で、スーパーやディスカウントストアでは「◯◯%OFF」や「今だけこの価格」といった表示を目立たせることで、価格先行の効果を活用し、消費者に「これは買うべき商品だ」と認識させることができます。
ただし、消費者は、価格を先に見ることで「この値段で本当に買う価値があるのか?」という思考にシフトするリスクもあります。そのため、単に割引率をアピールするのではなく、その価格がなぜお得なのかを具体的に示すことも重要です。
2.ECサイト・ネットショップ
ファッションやコスメなど、感情的な魅力が購買を左右する商品では、価格よりもビジュアルやストーリー性を前面に出すことが望ましいです。
消費者はこれらの商品を選ぶ際、「この商品を使うことで、どのような体験ができるのか」「ブランドの世界観に共感できるか」といった要素を重視します。
そのため、商品の画像やモデルの着用写真、ライフスタイル提案を充実させ、価格情報は後から提示する方が、購買意欲を引き出しやすくなります。
これに対し、実用的な商品を販売する場合、価格を先に提示することで「この価格でこの商品はお買い得なのか?」という視点で判断されやすくなります。
例えば、家電製品やオフィス用品のように、機能性やコストパフォーマンスが重要視される商品では、価格を強調したレイアウトが効果的です。
BtoBビジネスにおいても有効な知見
今回の実験が示す知見は、実店舗やネットショップだけではなく、サブスクリプション型ビジネス等にも活用できます。
たとえば、月額料金を最初に見せる場合と、サービスの魅力を先に伝えた後に料金を提示する場合とでは、契約率に違いが出る可能性があります。
もし、自社のサービスが「実用性」に重点を置いているのであれば、価格を先に示し、その後に「コストパフォーマンスの高さ」を伝えることで、顧客に「この価格でこれだけの価値がある」と納得してもらいやすくなります。
一方で、エンターテインメント性やブランドのストーリーが重要な場合は、商品の魅力を先に伝える方が効果的でしょう。
さらに、BtoBビジネスにおいても、この考え方は有効です。企業向けの製品やサービスは、機能性やコストパフォーマンスが重視される傾向にあります。
そのため、導入コストやROI(投資対効果)を先に伝えることで、価格を「コスト」ではなく「投資」として捉えてもらうことができます。
特に、意思決定プロセスに時間の掛かる業界では、初期段階で価格情報を提示し、その後に具体的な価値を示すことで、合理的な判断を促すことができます。
このように、「価格と商品、どちらを先に提示するか」という視点は、単なる消費者向けの戦略にとどまらず、あらゆるビジネスの販売手法に応用できます。
自社の商品やサービスの特性を見極め、適切な提示順序を設計し、より効果的な販売戦略を構築してください。
参考文献:Karmarkar, U. R., Shiv, B., & Knutson, B. (2019). Cost Conscious? The Neural and Behavioral Impact of Price Primacy on Decision Making.