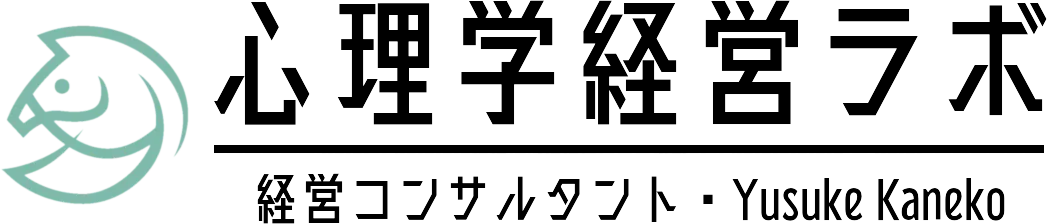多くの企業が導入している「社員表彰制度」。
勤怠が良好な社員や、業績を上げた社員を表彰することで、やる気を引き出し、職場の雰囲気を良くすることが目的とされています。
しかし、こうした制度が、かえってモチベーションを下げ、生産性を落としてしまうことがあるのをご存じでしょうか。
表彰制度が社員の行動や意欲にどのような影響を与えるのか、実際の企業データを用いて詳しく分析した、カリフォルニア大学リバーサイド校のティモシー・グブラー博士らの研究があります。
この研究結果は、多くの企業にとって警鐘を与えるものとなっています。
表彰でやる気が出るのは一部の人だけ
この研究では、アメリカ中西部にある産業用クリーニング工場で、月に一度「無遅刻・無欠勤」の社員を対象に、75ドル相当のギフトカードを抽選で贈る表彰制度が導入されました。
この制度は、企業側の狙いどおり、特にこれまで遅刻や欠勤の多かった社員たちに対して、一定の効果を発揮しました。
表彰されるために、出勤態度を改め、時間どおりに出勤しようと努力するようになったのです。
しかしながら、その効果は継続的なものではありませんでした。
制度のルールにより、たった一度の遅刻や無断欠勤でその月の抽選対象から外れてしまうと、そうした社員たちは即座に元の行動パターンへと戻ってしまったのです。
つまり、表彰制度がもたらす動機づけは表面的なものであり、長期的な行動変容や内発的な意識改革にはつながらなかったということです。
また、注目すべきは、その行動改善すらも「真の改善」とは言えなかった点です。たとえば、社員たちは「5分以内の遅刻ならセーフ」というルールを利用し、ギリギリのタイミングで出勤するようになったのです。
このように、本質的な責任感ではなく、「ルールに引っかからないように動く」というゲーム感覚で行動していた実態も明らかになりました。
表彰制度がまじめな社員のモチベーションを下げる
一方で、より深刻な影響を受けたのが、もともと遅刻や欠勤がほとんどなく、責任感を持って誠実に働いていた、いわゆる「まじめな社員」たちでした。
彼らは表彰制度の導入により、むしろモチベーションが下がってしまったのです。
その理由は「不公平感」にあります。
長年にわたり、特別な報酬や評価がない中でも自発的に努力し、周囲を支えてきた社員たちにとって、制度開始以降、これまで勤怠の悪かった社員が急に「表彰対象者」として名前を挙げられ、時には賞賛されてスポットライトを浴びる様子は、決して納得できるものではありません。
こうした社員たちは「自分たちは何の見返りもなくコツコツ頑張ってきたのに、今さら改善した人だけが評価されるのか」と感じるようになりました。
そして、「頑張っても報われない」「だったら、もう頑張らなくてもいいのではないか」という心理が広がってしまったのです。
他の仕事にも悪影響が及ぶ「スピルオーバー効果」
さらに驚くべきことに、表彰の対象となっていなかった業務にまで、その悪影響が広がりました。
このような現象は「ネガティブ・スピルオーバー効果(負の波及効果)」と呼ばれます。
今回の制度では、「出勤状況(遅刻・欠勤)」が評価の基準でした。
しかし、表彰制度によって不満を抱いた社員たちは、洗濯作業や仕分け作業といった本来の業務のパフォーマンスまで落としてしまったのです。
研究では作業効率が平均で約8%も低下したことが確認されています。
これは、単なるやる気の低下ではなく、職場全体への信頼感や、組織への帰属意識が損なわれた結果と見ることができます。
表彰されないことに対する落胆が、出勤以外の仕事にも悪影響を及ぼしてしまったのです。
【関連】社員のモチベーションが低下する原因!割引キャンペーンをしているせいだった
表彰制度の終了後も残った悪影響
こうした結果から見えてくるのは、表彰制度は単なる「ご褒美」ではないということです。
組織文化や社員同士の関係性、さらには職場全体の空気感にまで大きな影響を及ぼす「両刃の剣」なのです。
実際、研究に協力した工場のマネージャーたちは、制度終了後に「以前からまじめに働いていた社員たちが不満を抱えていた」と語っています。
とくに表彰の抽選で選ばれたのが、かつて出勤態度に問題のあった社員であることが多く、誠実に働いてきた社員たちにとってはその事実自体が強い失望につながったという証言もありました。
また、制度終了後も効率の低下が回復せず、一部の社員には長期的な悪影響が残ったことも確認されています。
一度でも社員のモチベーションが下がってしまうと、それを元の水準に戻すのは非常に困難なのです。
売上の表彰に関しても要注意
今回の研究は、無遅刻無欠勤に関するものでしたが、売上などの業績を上げた社員を表彰する制度を設けるときも注意が必要です。
競争が激化することで、社員同士のチームワークが悪くなったり、常に同じ社員ばかりが表彰されることで、他の社員のモチベーションが下がることもあります。
企業が表彰制度を活用する際には、目先の効果だけでなく、社員の多様な価値観や動機づけの仕組みを理解し、長期的な視点から制度設計を行う必要があります。
見えない心理的コストを見過ごしてしまえば、かえって組織の健全性を損ねてしまうのです。
個人的な意見としては、最初からやる気に満ち溢れた優秀な社員が集まっているような会社であれば、表彰制度がモチベーションにつながることも多いのかなと思います。
それと、その会社で表彰されることに価値があると思えるかどうかも重要です。「こんな会社で表彰されても嬉しくないしなぁ…」と思われているような会社では、表彰制度を導入しても、効果は期待できません。
まずは、社員全員が「ここで評価されたい」と思えるレベルまで、会社そのものの質を上げましょう。
参考文献:Timothy Gubler, Ian Larkin, et al. (2016). Motivational Spillovers from Awards: Crowding Out in a Multitasking Environment.