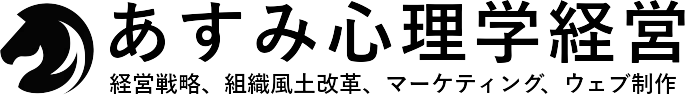ネットに投稿された、たったひとつのレビューがビジネスの未来を左右する――そんな時代に私たちは生きています。
特に旅行や観光のように、「一度きりの体験」となる可能性が高い分野では、不安も大きくなりがちで、ネガティブな口コミが与えるインパクトは計り知れません。
経営者やウェブ担当者の中には、「レビューはたくさんあるし、一つや二つ悪い声があっても仕方ない」と思っている人もいるかもしれません。
しかし、そのたった一つの悪評こそが、顧客の「行動」を止める最大のブレーキになるのです。
今回ご紹介するのは、旅行者の意思決定における「ネガティブレビューの影響力」を科学的に解明した、インドのTAパイマネジメント研究所の研究チームによる実験です。
悪いオンラインレビューの影響を調べる
この実験では、「ネガティブな口コミ(悪い評価)」が、旅先の印象や「そこに行きたい気持ち」にどのような影響を与えるのかを調べました。
口コミの中でも、特にフォーカスしたポイントは、「どれくらい詳しく書かれているか」と「書いた人がどれくらい信頼できそうか」という2点です。
参加者は「SonnetHill(ソネットヒル)」という名の観光地を評価するよういわれました。
この場所は実際には存在しない架空の場所ですが、インドの人気観光地のひとつをもとに風景写真や紹介文が含まれたパンフレットを用意し、参加者に実在の場所であると思わせました。
実在の場所を使わなかったのは、参加者がその場所について既に知っていた場合、先入観が入ってしまう可能性があるからです。
観光地を評価するにあたり、参加者は、5つのグループに分けられ、以下の種類の悪いオンラインレビューのどれかを見せられました。1つのグループは比較のために何も見せられません。
- 詳細なレビュー×信頼できる投稿者
- 詳細なレビュー×信頼できない投稿者
- 簡単なレビュー×信頼できる投稿者
- 簡単なレビュー×信頼できない投稿者
- レビューを見ないグループ(比較対照用)
レビューを読んでもらったあとで、以下のことについて質問しました。
- オンラインレビューはどのくらい信用できたか
- 旅行先にどんなイメージを持ったか(頭での印象と感情的な印象)
- 実際にその場所に行ってみたいかどうか
すべての質問は、「まったくそう思わない」から「とてもそう思う」まで7段階で答えてもらいました。
また、参加者が実際に「詳しいレビュー」と「簡単なレビュー」の違いをちゃんと感じてくれたかどうかをチェックする質問も入れていました。
これらのデータを分析したところ、以下のことが分かりました。
「詳細な悪いレビュー」は信じられやすい
この研究でまず明らかになったのは、「どれだけ詳細に書かれているか」が、そのレビューの信頼性に大きく関係しているという点です。
具体的な描写が多く含まれているレビューは、読んだ人に「これは実際に体験した人が書いているに違いない」と感じさせます。
たとえば「ホテルの部屋が汚かった」よりも、「ベッドのシーツにシミがあり、シャワーの水圧が非常に弱かった」といった詳細な記述の方が、信ぴょう性が高く感じられるのです。
さらに、誰がそのレビューを書いているのかという「情報源の信頼性」も重要なポイントです。
たとえば、投稿者のプロフィールに職業や過去の投稿履歴、滞在経験、旅行先の訪問数などが記載されていると、そのレビューの説得力が格段に増します。
逆に、匿名で一度しか投稿していないようなアカウントのレビューは、たとえ内容が具体的でも「本当なのかな?」と疑われがちです。
これはSNSの世界でもよくあることなので納得しやすいかと思います。実名で日々発信している人の投稿は信頼されやすく、アイコンもなし・投稿もなしのアカウントが突然何かを発信しても、なかなか信用してもらえません。
それと同じように、旅行のオンラインレビューにおいても「発信者の顔が見えるかどうか」が重要視されていることがわかります。
年齢によってオンラインレビューの影響は異なる
この研究で特に興味深かったのは、「レビューの受け取り方が世代によって異なる」という点です。
実験では、3つの世代にわけて影響を分析しており、それぞれ以下のような傾向が見られました。
ベビーブーマー世代(60歳以上)
高齢の旅行者は、ネガティブな情報に対して特に敏感であり、詳細に書かれたネガティブレビューを読むと、その内容を強く受け止める傾向がありました。「もし自分が同じような目にあったらどうしよう」と、リスクを避けようとする気持ちが働き、旅行への意欲が大きく低下する結果となりました。
X世代(40~50代)
この世代も、詳細に書かれたネガティブレビューを見ると、旅行への意欲が大きく低下する傾向がありました。「こんなに悪い体験があったのなら、行くのはやめておこう」と、より慎重に判断する姿勢が見受けられました。
ミレニアル世代(20~30代)
ミレニアル世代は同じ詳細なネガティブレビューを読んでも、それほど旅行意欲が下がることはありませんでした。むしろ、「これはこの人にとっての悪い体験かもしれないけど、自分には関係ないかも」と柔軟に受け取っているようです。
この違いは、世代によるリスク回避志向や、情報の処理スタイルの違いに起因していると考えられます。年齢が上がるほど、「失敗したくない」という気持ちが強くなり、ネガティブな情報により敏感になる傾向があります。
一方、ミレニアル世代はデジタルネイティブとして、日々膨大な量の情報にさらされており、その中で自分なりに「必要な情報だけを選び取る」力が育っているのかもしれません。多少の悪評は「参考程度」に見る傾向があるようです。
頭と心に残る「イメージ」が旅の意思決定を左右する
さらに注目すべきなのは、オンラインレビューを読むことによって「目的地のイメージ」が形成されるという点です。
レビューの信頼性が高いほど、読者の頭の中にはその場所についての「認知的イメージ」(=その場所に対する事実ベースの理解や評価)と、「情緒的イメージ」(=その場所に対して抱く感情や印象)がより強く、より鮮明に浮かび上がってきます。
たとえば、「レビューに書いてあったように道がゴミだらけで、スタッフの対応も最悪だったらどうしよう…」という具体的なイメージが形成されることで、「行きたい」という気持ちは自然と薄れていきます。逆に、ポジティブなレビューであれば、「ここは安心して楽しめそう」という明るい印象を受けて、訪問意欲が高まるのです。
つまり、レビューは単なる「評価」ではなく、旅行先に対する心象風景をつくり出す情報源になっているということです。
そして、そのイメージこそが、最終的に「行く・行かない」の判断を決定づけているのです。
オンラインレビューは未来の顧客を迎え入れる玄関口
この研究の結果は、ネガティブなオンラインレビューが単なる「悪評」ではなく、消費者の意思決定に深く関わる「意思形成の材料」であることを示しています。
特に注目すべきは、レビューの影響が年齢などのターゲット属性により異なる点です。
すべての顧客が同じように情報を受け取っているわけではありません。この違いを無視して一律の対応をしてしまうと、顧客との信頼関係を築くどころか、かえって信頼を損ねるリスクすらあります。
さらに、研究では「感情的なイメージ」が訪問意図に強く影響していたことも明らかになっています。
レビューを通じて「不快だった」「怖かった」といった感情が伝わると、事実よりもその感情が訪問の意思決定に影響するのです。この点は、レビュー対応において単なる事実の訂正ではなく、感情への共感や安心感を与える表現が求められることを示唆しています。
企業に求められるのは、デジタル上に散在する「声」の中から、誰のどんな声が意思決定に響いているのかを見極め、的確に対応する感度と戦略です。
オンラインレビューは、企業と顧客の接点のひとつであると同時に、未来の顧客を迎え入れる玄関口でもあります。その価値を、今一度見直す時ではないでしょうか。
参考文献:K. Pooja, Pallavi Upadhyaya. (2025). Does Negative Online Review Matter? An Investigation of Travel Consumers.