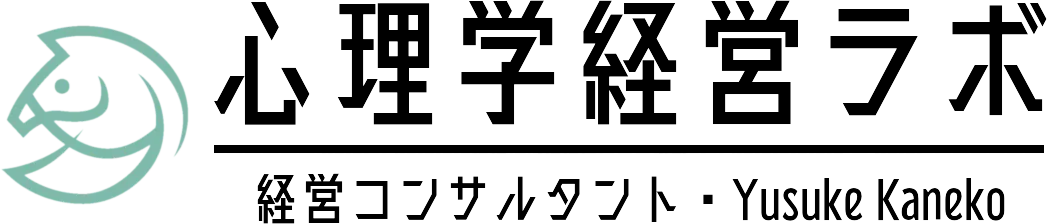技術革新のスピードが加速するなか、企業が生き残るには、外部からの知識をいかに取り込み、活用していけるかが鍵となります。
特に、資源や人材に制約のある中小企業においては、外部の知識を意味のある形で内在化し、自社の強みに転換していく力が求められます。
このような能力を「知識吸収能力(アブソープティブ・キャパシティ)」と呼びます。
知識吸収能力(アブソープティブ・キャパシティ)とは
知識吸収能力(アブソープティブ・キャパシティ)とは、企業が外部から得た新しい知識をうまく取り込み、それを理解し、自社の中で活用して成果につなげる力のことです。
ただ情報を集めるのではなく、それを実際の行動やイノベーションに結びつけるところまでを意味します。
この概念は、1990年に経営学者のウェスレイ・M・コーエンとダニエル・A・レビンソールによって初めて提唱され、現在では企業の競争力や革新力に欠かせない重要な理論とされています。
ミネソタ大学のシェイカー・A・ザフラ教授によれば、知識吸収能力は以下の4つの段階に分けられます。
- 取得(Acquisition)
外部から価値のある知識を探し、手に入れる力
例:顧客やパートナー、大学からの情報取得 - 同化(Assimilation)
得た知識を理解し、自社の知識体系に統合する力
例:社内での情報共有、分析、会議など - 変換(Transformation)
外部知識と既存の知識を組み合わせ、新しい洞察や方法を生み出す力
例:新しい技術と自社の強みを融合して製品を改良する - 活用(Exploitation)
組織のプロセスや製品、サービスにその知識を応用し、商業的成果に結びつける力
例:新製品の市場投入、生産性向上、新しいビジネスモデルの実行
この4つが上手くつながっていくことで、企業は時代の変化に強くなり、イノベーションも生まれやすくなります。
【関連】ナレッジシェアを自然に生む職場とは?社会的マインドフルネスの力
アウェアネスと知識吸収能力
中小企業が知識吸収能力を成長させるためには、どうすれば良いのでしょうか?
その参考となる、ブリストル大学ビジネススクールの研究チームによる調査があります。
この調査では、イギリス南西部にある43の中小製造業(主に航空や先端技術系の企業)を対象に調査が行われました。
まずは、各企業の経営者や上級管理職にインタビューをして、知識吸収能力の各段階における具体的な取り組みや、学ぶ姿勢について確認しました。
ここで注目したのが、「アウェアネス(Awareness)」という概念です。
アウェアネスとは、「知識を大事だと感じている」「学ぶことに関心がある」といった、意識や意欲のことです。
これは企業にとっての「学ぶための土台」とも言えます。
アウェアネスが高い企業は知識吸収能力も高い
得られたインタビューの内容をもとに、アウェアネスが、どれくらい組織の知識吸収能力に影響を与えてしているかを分析しました。
その結果、アウェアネスが知識吸収能力の発展において、重要な役割を果たしていることが明らかになりました。
まず、アウェアネスが高い企業の中でも、「学ぶことが組織の役に立つ」としっかり理解している企業ほど、「取得→同化→変換→活用」という知識吸収の一連の流れを、うまく進められていることがわかりました。
逆に、アウェアネスが低い企業では、情報を手に入れることはできても、それを自分たちのやり方に合わせたり、新しい工夫につなげたりといったことが、できていないことが分かりました。
さらに、外部情報の「取得」「変換」の段階には、アウェアネスの情動面(学びへの意欲や関心)も影響していました。
つまり、「学びたい」という気持ちがあるかどうかが、最初に知識を集めたり、それを自社のやり方に合わせたりするのに大きな役割を果たしていたのです。
また、多くの企業で見られた特徴としては、知識を同化する(理解して受け入れる)ところまではうまくできていても、それを変換(自社用に応用する)したり、活用(実際の仕事に使う)したりする部分で躓いているという点が挙げられます。
これは、新しい知識を受け入れることはできても、それを現場で本当に使えるようにするには、時間も費用も手間もかかることが要因といえます。
特に中小企業の場合、こうした部分に割ける余裕がないことが多く、結果として知識がうまく活かされないまま終わってしまうケースも少なくありません。
中小企業が知識吸収能力を強化するには内発的動機づけが必要
中小企業が知識吸収能力を強化するために、重要となるのはアウェアネスの内的側面をどう育てるかということです。
本研究では、アウェアネスを組織全体のものとして捉えていました。
しかし、実際にそれらを形成するのは、社員一人ひとりの「内発的動機づけ(自分がやりたいからやるという内側から湧き出る意欲)」です。
社員の「自ら進んで学びたい」「変化に貢献したい」という意欲の有無が、アウェアネスを高め、知識の取得や同化、変換、活用に大きく寄与します。
経営層が知識の導入に積極的であっても、現場で働く社員がその知識の価値を感じられていなければ、学習のサイクルは組織全体に広がりません。
逆に、現場の社員が自ら問題意識を持ち、外部からの知識を「自分ごと」として捉えることができれば、その知識はただの情報で終わらず、実践的な改善やイノベーションの源泉となります。
このような内発的動機づけを育むには、心理的安全性の高い組織風土や、挑戦を歓迎する文化づくりが求められます。
また、個人の成長を促すキャリア支援やフィードバック、学習の成果を正当に評価する仕組みも欠かせません。
知識の共有や活用が評価される環境であれば、社員は自然と「学ぶこと」や「新しい知識を活かすこと」に前向きになるはずです。
さらに、近年ではデジタル技術の進展により、知識の取得や共有のあり方も大きく変わってきています。ウェビナー、社内の情報共有ポータル、AIを活用したシステムなど、企業の学習環境を豊かにするツールは多岐にわたります。
これらをうまく組み合わせることで、リソースの限られた中小企業であっても、柔軟かつ継続的な学習基盤を構築することが可能です。
中小製造業が不確実性の高い市場環境の中で持続的に成長していくためには、単なる業務の改善だけでなく、学習と変化を日常の営みとして組織に根付かせる工夫が不可欠です。
【関連】AI(人工知能)に注力している企業は儲かっているのか分析した論文
参考文献:
・Shaker A. Zahra and Gerard George. (2002). Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension.
・Mohammed Saad,Vikas Kumar, John Bradford. (2016). An investigation into the development of the absorptive capacity of manufacturing SMEs.