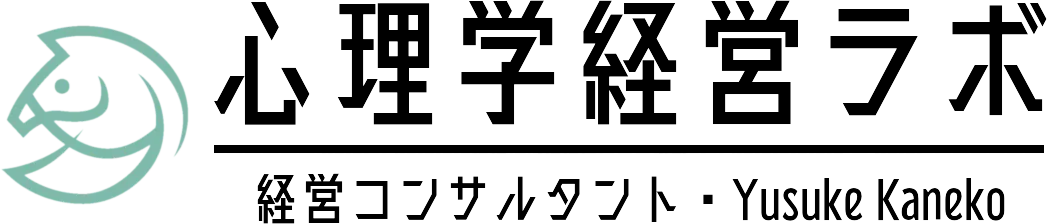会社の業績を上げるために必要なものといえば、社員のスキルや経験、戦略などが真っ先に思い浮かぶかもしれません。
しかし、それらと同等以上に重要なのに、見落とされがちな要素があります。
それは、快適な職場環境と社員の気分です。
これらの要因が業績に影響を与えるということが、具体的な数字としても確かめられています。
大手通信会社の社員を対象とした調査
社員の気分や職場環境が、業績にどんな影響を与えるのか検証した、エラスムス・ロッテルダム大学のクレマン・ベレット准教授らの研究があります。
イギリスの大手通信会社ブリティッシュテレコムの電話セールス部門で働く1,793人の社員を対象に、6か月間にわたって調べたものです。
この研究では、社員の気分を測るために、週に1回の簡単なアンケートが導入されました。「今週はどれくらい良い気分だったか?」という質問に対して、5段階で答えるものです。
また、社員の気分に影響を与える環境要因として「天気」と「オフィスの窓」も考慮しました。
コールセンターは全国に11カ所ありますが、大きな窓から外の天気がよく見える建物もあれば、窓がほとんどない暗い建物もあります。そして、天気も異なります。
つまり、ある社員は快晴の景色を見ながら働き、別の社員は曇り空や雨を眺めながら仕事をする、という状況が生まれます。
実際に、雨や曇りの日に外の景色がよく見える社員ほど、気分が落ち込みやすくなるという結果が出ました。
社員が良い気分になると売上が増える
上記で得られた社員の気分と、営業データを比較しました。
1週間に何件の契約を獲得したか、1時間あたりの電話件数、成約率などにどんな影響が出たかを検証したのです。
その結果、社員の気分と職場環境の快適さを合わせた10段階のスケールが1段階上がると、その週の売上が約3件増えることが分かりました。これは平均売上の約12%に相当します。
社員が良い気分になると、顧客との会話がうまく進み、成約率が上がる傾向がはっきりと見られました。
また、多少ではありますが、時間の使い方が効率的になり、電話の件数が増えたり、スケジュール通りに行動する傾向も強まりました。
とはいえ、成果の大部分は「顧客対応の質の向上」によるものでした。
【関連】なぜ高層階のヘッジファンドほどリスクを取りやすいのか?調査が明かす驚きの理由
企業が取り組むべきこと
以上の結果から、社員の気分を「業績に影響する経営資源」として捉え、戦略的に職場環境の改善に取り組む必要があることがわかります。
以下に、企業が現実的に取りうる対策をいくつか説明します。
1.社員の気分を「見える化」する
社員の気分や感情は目に見えませんが、日々のパフォーマンスに確実に影響します。そのため、まずは社員の状態を把握できる仕組みを整えることが出発点となります。
たとえば、週に1回、1分で答えられる簡単なアンケートを導入したり、日報の末尾に「今日の気分」を記録する欄を設けたりするだけでも十分です。
営業やカスタマーサポートなど、顧客対応が主な業務である職種では、感情の変化が成果に直結する傾向があります。
こまめに気分の変化を記録・可視化することは、状況を早期に察知し、適切な対応につなげるための第一歩になります。
2.オフィス環境を整える
人の気分は、職場の物理的な環境によっても左右されます。
今回の研究では、外の天気が目に入ることで気分が上下することが明らかになりました。
これを踏まえると、自然光が入りやすいレイアウトに変更する、窓際の席を有効活用する、照明を温かみのあるものに変えるなどの工夫が効果的です。
もし窓の増設が難しい場合は、観葉植物を置く、木材などの自然素材を使う、明るい壁紙や装飾で視覚的な快適さを演出することでも、心理的な負担を軽減できます。
休憩スペースにも配慮し、社員が気分転換できる場所を確保することも重要です。
3.上司や管理職が「感情」に意識を向ける
現場のマネージャーやリーダーが、社員一人ひとりの感情に気を配ることは、組織の健康を保つうえで欠かせません。
体調と同じように、気分の不調にも波があります。ちょっとした声かけや、ねぎらいの言葉、相手の話を丁寧に聞く姿勢が、社員に安心感を与えます。
また、調子の悪いときに遠慮なく相談できるような信頼関係や心理的安全性を築くことも、長期的に見て気分の安定につながります。
マネジメントにおいて「感情」を無視しない姿勢が、パフォーマンスを引き出す土台になります。
4.感情を扱う研修や仕組みを取り入れる
感情の扱い方や、自分の気分を整える力は、意識的なトレーニングによって高めることができます。
マインドフルネス研修やストレスマネジメント講座、感情の整理を助けるワークショップなどは、社員自身が自分の感情をうまくコントロールできるようになるための有効な手段です。
また、社内でポジティブなフィードバックを積極的に取り入れたり、感謝や称賛を伝え合う文化を育てたりすることも、社員のメンタルを支える環境づくりにつながります。
これらの取り組みが単なる「癒し」ではなく、「業績に貢献する仕組み」であるという意識を、全社的に共有していくことが大切です。
5.感情への配慮を人事戦略の一部に組み込む
社員に快適に働いてもらうには、一時的な取り組みだけでなく、組織全体の制度設計にも反映させることが求められます。
たとえば、フレックスタイムやリモートワークの導入、キャリア形成の支援、育児や介護との両立を支援する制度などが該当します。
福利厚生の充実も有効ですが、単に「満足度を上げる」ことが目的ではありません。
社員一人ひとりが気持ちよく働ける状態を維持し、そのうえで本来の力を発揮できるようにすることが、真の狙いです。
人事制度の中に「感情面への配慮」という視点を明確に位置づけることで、持続的な業績向上につながる体制が整います。
【関連】職場環境が経営を左右する?銀行支店における従業員態度と成績の相関を分析
人的資本の充実が業績につながる
近年では、投資家や市場も「人的資本の充実」を企業評価の一部として注目するようになっており、従業員の感情やウェルビーイングは、もはや無視できない経営指標のひとつです。
米国証券取引委員会(SEC)では、上場企業に対して人的資本に関する情報開示を義務づけており、日本でも人的資本経営の重要性が広がりつつあります。
このような背景を踏まえると、社員の感情や気分を把握し、それに配慮した制度や環境を整備することは、今後の企業経営において避けて通れないテーマになりつつあります。
業績との関係がデータで示されるようになった今、企業は感情を管理の対象として捉える必要があると言えます。
参考文献:Clément S. Bellet, Jan-Emmanuel De Neve, George Ward. (2023). Does Employee Happiness Have an Impact on Productivity?