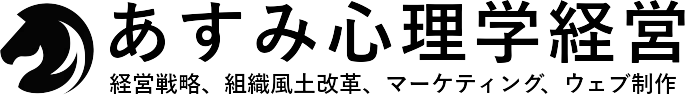社員が「会社との価値観が合わない」と感じたときの悪影響は、モチベーションが下がるだけではありません。
集中力や判断力も低下し、ヒューマンエラーや事故を引き起こすこともあります。
今回は、価値観のズレが職場にどのような悪影響を及ぼすのか、そして事故やバーンアウトを防ぐために企業が取るべき対策についてお伝えします。
価値観の不一致が職場にもたらす影響
そもそも、価値観とは何でしょうか。それは「何を大切にして生きているか」という行動原理や判断基準のことです。
「正直であること」「家族を優先すること」「結果を出すこと」「チームで協力すること」など、社員によって大切にしていることは異なります。
一方で、組織にも価値観があります。例えば、「挑戦し続ける」「世の中を良くする」といったビジョンなどがそうです。価値観として明示していなくとも、会社の理念や、評価制度、経営層の言動の中に、それが色濃く現れます。
この個人と組織の価値観が一致していると、社員は職場で自分らしく振る舞え、心理的安全性が高まります。仕事へのやりがいを感じ、モチベーションも上がるでしょう。逆に、価値観が合わないと、社員は疎外感やストレスを感じやすくなります。
価値観の不一致は、コミュニケーションや判断にも影響します。「自分が大切にしていることが評価されない」「組織の方針が納得できない」と感じたとき、人は受け身になったり、表面的に合わせるだけになったりします。
それが続くと、業務中の事故やバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥ることもあります。
価値観が合わないときの悪影響
組織と社員の価値観が合わないと、どのような影響が出るのか調べた、ESADEビジネススクールの研究チームによる調査があります。
この調査では、大規模な病院で働く看護師約200人を対象にアンケートを行い、自分と組織の価値観のズレを確認しました。
具体的には下記の項目を、自分がどれだけ重視しているか、組織はどれだけ重視していると感じるかを評価しました。
- 経済的価値(例:経済的報酬、目標達成、競争意識、生産性、秩序維持)
- 倫理的価値(例:助け合い、ワークライフバランス、職業倫理、公平性)
- 情緒的価値(例:思いやり、熱意、幸福感、嘘をつかない)
上記に加え、バーンアウト(燃え尽き症候群)の兆候と、業務中の事故(投薬ミスや医療機器の誤使用、患者誤認etc)が起こる可能性についても、確認しました。
その結果、情緒的な価値の不一致は、業務中の事故を起こす可能性を高める傾向があることが分かりました。さらには離職意図も高めていました。
経済的価値と倫理的価値不一致はバーンアウトを高め、さらにそのことが離職意図や事故傾向を高める関係にあることも分かりました。
なぜ価値観の不一致が事故やバーンアウトにつながるのか
価値観の不一致が事故やバーンアウトにつながる理由は、人間の心理と行動の根本的な仕組みにあります。
まず、価値観とは「何が正しいか」「何が大切か」という個人の判断基準や行動原理です。
これが職場の価値観と一致していると、社員は自分の行動や決断に確信を持つことができます。例えば、協力を大切にする人がチームワーク重視の職場で働くとき、行動と環境が調和し、安心感や充実感を得やすくなります。それによって仕事のパフォーマンスも高まります。
しかし、個人の価値観と職場の価値観が大きくズレている場合、例えば「誠実さ」を大切にする社員が不正を黙認する風土の中で働いているとき、その社員は強い心理的葛藤を抱えることになります。
この葛藤は、「認知的不協和」として知られる心理状態で、精神的負荷を生み、ストレスや無力感、怒りや諦めの感情を引き起こします。
この状態が長引くと、次第に自分の価値観を抑え込み、組織に合わせるためにエネルギーを消耗するようになります。すると心身の疲労が蓄積し、いわゆるバーンアウト(燃え尽き症候群)に至ります。
バーンアウトは集中力や注意力の低下を伴うため、結果として仕事中の判断ミスや確認漏れが増え、事故やヒューマンエラーのリスクを高めるのです。
情報共有も不十分になる
さらに、価値観の不一致は職場での孤立感や疎外感を生み出します。
自分の大切にしていることが理解されないと感じると、人は周囲とのコミュニケーションを減らし、相談や報告、確認を怠るようになります。
こうした状況が続くと、チーム全体での情報共有が不十分になり、安全確認の漏れや誤解による事故が起こりやすくなります。
つまり、価値観の不一致は社員の心理的負荷を高め、その負荷が心身の疲弊や無気力を生み出し、さらにコミュニケーション不足や注意散漫という具体的行動変容を引き起こすため、事故やバーンアウトにつながるということです。
事故やヒューマンエラーを防ぐために企業ができること
価値観のズレによる事故やヒューマンエラーを防ぐために、企業はどのような取り組みをすればよいのでしょうか。
1.採用段階での価値観の擦り合わせ
まず重要なのは、採用段階での価値観の確認です。採用ではスキルや資格、経験が重視されがちですが、それと同じくらい「この組織の価値観と合うか」を見極める必要があります。どれほど高いスキルを持った人材でも、組織の価値観と合わなければ力を発揮できません。
面接では、応募者がどのような価値観を大切にしているかを丁寧にヒアリングし、組織の理念や文化、業務方針との相性を確認する必要があります。
例えば、成果主義を徹底している企業であれば、個人としても結果への執着心や数値達成への責任感を強く持つ人材の方が適応しやすいでしょう。一方で、チームワークや協力を重んじる組織であれば、協調性や相手へのリスペクトを行動に移せる人が望まれます。
採用の入り口段階からミスマッチを回避する姿勢が大切です。
2.既存社員の価値観を共有する場をつくる
既存社員への価値観共有の場をつくることも必要です。
組織の価値観は経営環境や事業戦略の変化によって進化していくものです。そして、社員一人ひとりの価値観も、年齢、ライフステージ、家庭環境の変化に応じて変わることがあります。
入社時には強く感じていた会社への共感が、10年後には弱まっていることも珍しくありません。定期的に価値観に関するワークショップや対話型研修を行い、社員同士、そして上司と部下の間で「何を大切にしているか」「仕事をする上でどんなことに誇りを感じるか」を確認しましょう。
それが、お互いのズレに気づき、すり合わせることが可能になります。こうした場は、単なる研修というよりも、心理的安全性の向上やコミュニケーションの活性化にもつながります。
3.経営理念と実際のズレを見直す
経営理念や行動指針が単なるスローガンになっていないかも見直しましょう。
たとえば、「お客様第一」「挑戦し続ける」という言葉を掲げていても、実際の評価制度が売上数字や効率ばかりを重視していると、社員は混乱し、何が正しい行動なのか分からなくなります。
理念と評価制度、日々の業務運用との間に齟齬があると、社員は価値観不一致を感じ、仕事への誇りやモチベーションを失いやすくなります。
評価基準や昇格条件、業務プロセスに至るまで、理念と一貫した設計になっているか、見直してみましょう。
板挟みの管理職にも配慮する
最期に見落とされがちな視点があります。それは、現場の管理職やリーダー自身もまた「価値観の板挟み」に苦しんでいるということです。
例えば、経営層からは「利益を最大化せよ」と求められる一方で、現場からは「安全第一で無理な指示はしないでほしい」という声が上がる。こうした板挟みの中で、管理職は葛藤し、結果的にどちらにも十分に寄り添えなくなることがあります。
このリーダー層の価値観不一致は、判断の迷いや指示のブレを生み、現場に混乱やエラーを引き起こす温床となるのです。
だからこそ、価値観の一致を考える際には、一般社員だけでなく管理職への支援も欠かせません。リーダー研修の中で、本人の価値観と組織の価値観を整理し、両者をどう統合していくかを考える機会を持たせることが重要です。
さらに、経営陣がリーダー層に対しても価値観のすり合わせを行い、安心して意思決定できる環境を整えることが、組織全体の安全性やパフォーマンス向上につながります。
事故を減らし、強いチームを育てるために、企業は「価値観」という目に見えない部分にも注目する必要があります。それが、社員の心を守るだけでなく、組織の将来を守ることにもつながるのです。
参考文献:Yuanjie Bao, Rebekka Vedina, et al. (2012). The relationship between value incongruence and individual and organizational well-being outcomes: an exploratory study among Catalan nurses.