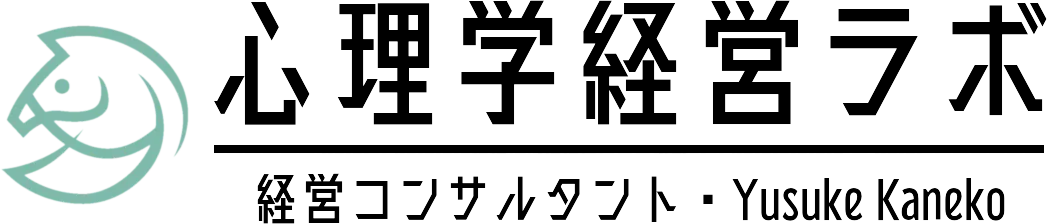一人の社員が辞めたら、なぜか他の社員も次々に辞めていった、という経験を持っている経営者もいるでしょう。
実はこれ、偶然ではありません。
複数の組織心理学の研究によって、退職が連鎖することが明らかになっています。
このような現象は専門的には「Turnover Contagion(離職の伝染)」と呼ばれ、企業にとって見逃せないリスクです。
Turnover Contagion(離職の伝染)
「離職の伝染」とは、一人の社員が退職を検討したり、実際に退職したりすることによって、その行動や気持ちが周囲の同僚にも影響を与え、他の社員の退職意欲が高まる現象のことです。
これは単なる偶発的な出来事ではなく、まるでウイルスが広がるかのように起こる点が特徴です。
この現象は、近年の組織行動論や社会心理学の研究によって明確に裏付けられてきました。
メンフィス大学のケイトリン・ポーター准教授らの研究によれば、職場内で誰かが「辞めたい」と口にしたり、転職活動の様子を見せたりすることが、他の社員にとっての「刺激」となり、職場環境への満足度を見直すきっかけになるとされています。
例えば「あの人が辞めるなら、自分も他の選択肢を考えていいのではないか」といったように、同僚の退職行動が自己のキャリア判断に直接影響を与えるのです。
このように、退職は個人の意志決定であると同時に、周囲との関係性や情報の受け取り方によっても大きく左右される社会的なプロセスでもあるのです。
他の社員の退職の予兆は目に見える
社員は日常の中で、無意識のうちに同僚の行動や態度の変化を観察しています。そして、些細な変化でも、それが「退職の兆候」として職場内に伝わることがあります。
たとえば、以前より明らかにやる気が感じられなくなったり、職場に対する不満をしきりに口にするようになったりすると、周囲は「この人は辞めるつもりかもしれない」と感じ取ります。
また、普段は残業をよくしていた社員が急に定時で帰るようになったり、髪型や服装をきちんとし出したりすると、他の社員の間で「あの人、面接なのでは?」という憶測が広がることもあります。
このような一連の行動は「Pre-Quitting Behaviors(事前離職行動)」と呼ばれ、退職の前兆とみなされます。
重要なのはこれらの行動が単なる個人の問題ではなく、周囲に対して「心理的な刺激」となる点です。
つまり、そうしたサインに接した同僚が自分自身の働き方や将来について考え直すようになるのです。これが、退職の連鎖が始まる「引き金」になると考えられています。
【関連】マーケティング担当者の離職がブランド力の低下を招く。477社の分析が明かす真実
心理的なメカニズム:なぜ伝染するのか?
社員の退職が他の社員にも影響を及ぼす背景には、私たち人間が持つ社会的な情報処理と比較行動の心理が深く関係しています。特に、以下の2つの理論が退職の連鎖を説明するうえで重要です。
1.社会的情報処理理論
人は物事を評価したり意思決定をする際、周囲の人々から得られる情報を手がかりにして判断します。これを「社会的情報処理理論」といいます。
職場では、上司や同僚といった周囲の人々が発する言動が社員自身の仕事への評価や満足度に大きく影響を与えます。
たとえば、ある社員が「最近この仕事にやりがいを感じない」「上司と合わない」といった不満を頻繁に口にするようになると、それを聞いた周囲の社員は「自分もそうかもしれない」と感じ始める可能性があります。特に、普段から信頼している同僚がそう発言すれば、その影響力はさらに増します。
このようにして、一人の不満やネガティブな評価が職場全体にじわじわと伝播し、「この職場はよくないのではないか」という共通の認識(社会的コンセンサス)が形成されていきます。
そして、その認識が広がることで、実際に離職を考える社員が増えていくのです。
2.社会的比較理論
人間には自分の考えや状況を判断するときに、他人との比較によって相対的な価値を見出そうとする傾向があります。これを「社会的比較理論」といいます。
特に職場では「自分と似た立場の同僚がどのような選択をしているか」が自身のキャリア判断に影響を与えます。
たとえば、年齢やスキル、社歴が近い同僚がもっと待遇の良い会社に転職したと知った場合、自分も「転職すれば今よりいい条件が手に入るのではないか」と考えるようになります。
これがいわゆる上方比較であり、「あの人にできたのなら、自分にもできるはずだ」という思考が生まれやすくなるのです。
また、同僚が辞めた理由が「やりがいのある仕事を見つけた」「ワークライフバランスが良くなった」といったポジティブなものであればあるほど、比較対象としての魅力は増し、残された社員の離職意欲も高まりやすくなります。
感情や雰囲気も伝播する
さらに、こうした情報や比較は単なる論理的判断だけでなく、職場の感情的な空気やムードにも影響を与えます。
誰かが「辞めたい」「もう限界だ」といった感情を表に出すと、それがチーム全体に重たい空気として伝わり、雰囲気自体がネガティブになります。
その結果、「ここにいても将来が見えない」「自分も何か行動しなければ」と感じる社員が増え、実際の離職という行動へとつながっていくのです。
退職の連鎖が起きやすい条件とは?
退職の連鎖が発生しやすいかどうかは、職場の状況や人間関係によって左右されます。
とりわけ注目すべきなのは退職した社員と残された社員の関係性です。辞めた社員と日頃から親しくしていたり、同じチームで密に連携していた場合、その影響は大きくなります。
また、辞めた社員が職場内で高く評価されていた場合や、能力のある社員であった場合も、「あの人が見切りをつけたなら自分も考えるべきでは?」という気持ちが広がります。
加えて、すでに職場内で複数の社員が仕事に対して不満を抱えていたり、雰囲気が沈滞していたりする場合、退職の伝染は一気に加速する傾向があります。
このような環境下では、たった一人の退職が引き金となり、短期間で連鎖的な退職が発生する可能性が高まります。
このように、関係性、社員の評価、退職理由、職場の空気といった複数の要素が組み合わさることで離職の伝染はより強力に、そして速やかに進行していくのです。
経営者・管理職に求められる対策:離職の連鎖を防ぐために
社員の退職をゼロにすることは不可能です。しかし、一人の退職が職場に波紋を広げ、次々と連鎖的な離職を引き起こすことはマネジメントの工夫によって予防または最小限に抑えることが可能です。以下では、実証研究をもとにした具体的な対策をご紹介します。
1.社内ネットワークを可視化し、「影響力のある社員」に注目する
社員一人ひとりの人間関係や情報の流れを把握するために、社内のネットワークに注目しましょう。たとえば、同僚からよく相談を受けている人や、チームのムードメーカーのような存在は目に見えない影響力を持っている可能性があります。
このような「キーパーソン」が退職する場合、残された社員に与える心理的影響は非常に大きく、離職の伝染が起きやすくなります。そのため、これらの社員が抱える不満やキャリア志向を日常的に把握し、早期に対話の場を持つことが重要です。
2.「火種のチーム」や不満が集中する部署を特定し、重点的にケアする
職場の一部に不満やストレスが集中している場合、それが局地的な離職の温床となるリスクがあります。従業員の満足度調査やエンゲージメントサーベイの結果を活用して、部署やチームごとの傾向を把握しましょう。
もし、ある部門で「評価が不公平」「仕事量が多すぎる」といった声が目立つようであれば、マネージャーとの面談や、業務の再配分、チームビルディングの実施など集中的な支援が必要です。早期に介入することで、ネガティブな空気が他部署に広がるのを防ぐことができます。
3.退職者の理由や背景をオープンに話し合い、誤解や不安を抑える
退職者が出た後、残された社員の間に「なぜ辞めたのか」「自分もそろそろ転職した方がいいのでは」といった憶測や不安が広がることがあります。こうした曖昧な情報が退職の連鎖の温床になるため、オープンなコミュニケーションが重要です。
可能な範囲で退職者の離職理由や今後の人員配置の見通しなどを共有し、社員の不安を和らげましょう。また、退職をポジティブに受け止めつつも「今いる社員を大切に思っている」ことを明確に伝えることで職場の安心感が保たれます。
4.離職後は「ステイ・インタビュー」で残る社員の声を聞く
「ステイ・インタビュー」とは退職者ではなく現在働いている社員に対して行う面談です。「何がこの職場に残る理由になっているか」「どんなことに不満を感じているか」「今後どのようなキャリアを望んでいるか」といった質問を通じて社員の本音を引き出すことが目的です。
退職が起きた直後にステイ・インタビューを実施することで、他の社員が同様の考えを持っていないかを把握でき、必要に応じて個別対応やフォローアップを行うことができます。
5.成長機会・報酬・キャリアパスを明示し、将来への安心感を提供する
「辞めよう」と考えるきっかけの多くは「このままここにいても成長できない」「評価されていない」といった将来への不安です。そのため、日頃から社員に対して成長の機会や報酬の仕組み、キャリアパスを具体的に伝えることが重要です。
たとえば「このスキルを身につければ昇格のチャンスがある」「新しいプロジェクトでリーダー経験ができる」など、自分の未来がここにあると実感できる環境づくりが退職の連鎖を防ぐ鍵となります。
退職の連鎖を止めるのは「人」の力
退職はたった一人から始まっても周囲の人々に無意識の影響を与え、組織全体に波及することがあります。
しかしその一方で、連鎖を止めるのも人と人との対話や信頼関係です。
日々の小さな違和感に気づき、声をかけ、耳を傾ける。その積み重ねこそが職場の健全な維持につながります。
経営者やマネージャーには、データと感性の両方を活かしながら、離職の連鎖を未然に防ぐ仕組みと姿勢が求められます。
参考文献:Caitlin M. Porter, James R. Rigby. (2020). The turnover contagion process: An integrative review of theoretical and empirical research.