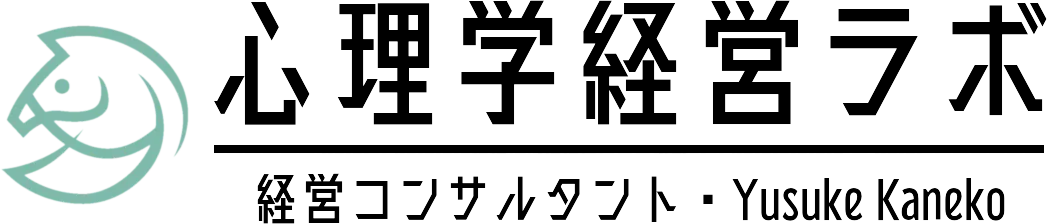「中小企業が生き残るには、イノベーションが不可欠だ」
そんな言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
新商品を開発したり、ユニークなサービスを打ち出したり、大企業にはできない大胆な挑戦を武器にしたり……
イノベーションは、資源の限られた中小企業にとって競争を勝ち抜く「切り札」とされがちです。
しかし、本当にイノベーションは、中小企業の業績向上につながっているのでしょうか?
過去の実証研究では、効果があるという報告と、逆に効果が見られないという報告が入り混じっており、明確な結論は出ていません。
イノベーションに力を入れたからといって、すべての中小企業が成功しているわけではないのです。
実際、研究開発に多額の資金を投じたのに業績が伸びない、外部と協業したものの結果が出ない、といった声も多々あります。
実はイノベーションによって、成果を上げやすい中小企業には特徴があるのです。
21,270社分のデータを統合し再分析(メタアナリシス)
イノベーションが中小企業の業績にどう影響するかを分析した、アイビー・ビジネススクールのニーナ・ローゼンブッシュ准教授らの研究があります。
この研究では、過去に行われた42件の実証研究(総サンプル数21,270社)を統合したうえで、再分析しています。(メタアナリシスという分析手法です)
ここでいうイノベーションとは、企業が新しい製品やサービス、業務プロセス、ビジネスモデルなどを導入する取り組み全般のことです。
具体的には、社内で新たに開発した商品を市場に出すことや、製造工程をより効率的に変えること、今までにない販売方法やサービス提供方法を取り入れることなどが含まれます。
単に「技術的にすごい発明をすること」だけでなく、既存の技術やアイデアを自社の文脈に合わせて応用することもイノベーションに含まれます。
今回の研究ではイノベーションを次の3つの視点から整理しています。
- 志向(戦略的な姿勢):企業がどれだけイノベーションを重視し、取り組もうとしているかという姿勢や方針
- 投入(プロセスへの投資):研究開発費や人材など、イノベーションに必要な資源にどれだけ投資しているか
- 成果(アウトプット):実際に生み出された新商品、新サービス、特許など、目に見える結果
これらが、中小企業の売上や成長にどのような影響を与えているかを分析しています。
中小企業のイノベーションを左右するもの
分析の結果、イノベーションは中小企業の業績に、プラスの効果をもたらすことが分わかりました。
具体的には、売上高や収益性、市場成長率が有意にプラスとなっていたのです。
ただし、イノベーションが業績にもたらす効果は一律ではなく、企業の特徴や環境によって大きく左右されることも、判明しました。
つまり、イノベーションが必ずしも中小企業の成長につながるとは限らず、いくつかの条件が揃ってはじめて効果が生まれるのです。
以下では、特に注目すべきポイントを解説します。
1.成果よりも「姿勢」が大事
中小企業がイノベーションから得られる利益は、具体的な成果物(特許の取得や新製品の発売)そのものよりも、組織としてイノベーションを重視する姿勢や戦略的志向に大きく左右されることが明らかになりました。
つまり、単発の「何を作ったか」ではなく、企業文化としてイノベーションを育てる土壌があるかどうかが、成果の有無を分ける鍵なのです。
具体的には、社員が新しいアイデアを提案しやすい風土、失敗を許容する文化、変化を前向きに受け入れる価値観が重要です。
経営者自身が「挑戦を歓迎する姿勢」を打ち出し、それを組織全体に根づかせることが、中長期的な成功につながるといえます。
【関連】現状維持バイアスを組織変革に応用する方法!従業員の抵抗を減らすための伝え方
2.お金をかければ成功するとは限らない
イノベーションと聞くと、まず思い浮かぶのが研究開発費用や人材投資です。しかし、研究ではR&Dなどに多くのリソースを投じた企業が、必ずしも業績を向上させているわけではない、という結果が出ています。
限られた予算や人手でも、しっかりと市場に新しい価値を届けた企業は、確実に業績を伸ばしていることがわかっています。
要するに、「どれだけお金を使ったか」ではなく、その資源をいかに有効活用し、現実の成果につなげられるかということです。
中小企業にとっては、少ない資源で「やりきる力」、つまり実行力が何より重要だといえます。
3.若い企業ほどイノベーションで伸びる
企業の年齢もイノベーションの効果を左右する要因のひとつです。
研究では、創業してからの年数が短い若いスタートアップやベンチャー企業のほうが、イノベーションによって業績を大きく伸ばしやすいことが示されています。
これは、若い企業は組織が硬直化していないため、意思決定のスピードが速く、「アイデアを試す→改善する→市場に投入する」というサイクルを短期間で回すことが可能な点が要因と考えられます。
また、過去のやり方に固執する文化がないため、必要であれば大胆なピボット(方向転換)が可能なことも、イノベーションによる成功率を高めることにつながっています。
4.外部との連携は注意が必要
「大企業や大学と組んでイノベーションを加速しよう」といったアプローチは、多くの中小企業が採用しています。
しかし、外部との連携が必ずしも業績にプラスとは限らないことが分かりました。その要因として以下のリスクが挙げられます。
- 意思決定のスピードが落ちる
- 調整コストが増える
- 知的財産権の管理が難しい
- パートナー企業に主導権を握られやすい
特に、立ち上げ間もない企業では交渉力や管理能力がまだ十分に育っていないことが多く、思ったような成果につながらない可能性があります。
まずは自社内での開発体制やノウハウを固めた上で、慎重に連携先を選ぶことが望まれます。
5.集団主義の文化圏の方が成功しやすい
文化的背景もまた、イノベーションの成否に大きな影響を与えます。
研究では、アメリカなどの個人主義的な文化よりも、アジアや南欧に見られるような集団主義的文化のほうが、イノベーションと企業業績との相関が強いという結果が得られました。
イノベーションには、商品開発だけでなく、チーム全体での協働や社外関係者との調整が不可欠です。
このような背景では、仲間意識や協調性を重視する文化のほうがプロジェクトを円滑に進めやすく、成果につながりやすいと考えられます。
また、集団主義文化ではイノベーションに取り組む企業数自体が少ないため、ひとたび成功すれば競争が少ない中で優位に立てるという利点もあります。
【関連】中小企業が大手企業に勝つためにアピールするべきキーワードとは?
経営者の「イノベーションは成功している」という錯覚にも注意
イノベーションは、中小企業にとって魅力的な成長戦略です。しかし、その効果は決して一様ではありません。
今回紹介した研究からは、イノベーションの効果は会社の年齢や文化、そしてどのように取り組むかによって大きく変わることがわかりました。
特に大切なのは、何を作ったかよりも、会社全体がどんな姿勢でイノベーションに取り組んでいるかです。
「挑戦を応援する空気があるか」「新しいアイデアを出しやすい雰囲気があるか」など、目に見えない部分が成果に大きく関わっているのです。
さらに、今回の研究ではイノベーションの成果をどう評価するかによって、効果の見え方が変わることも示されています。
たとえば、経営者が「当社はイノベーションの成果が出ている」と判断していても、実際の売上高や利益は他の要因によって上がっているだけということもあるのです。
つまり、イノベーションの成果を正しく評価し、次の戦略につなげるためには、自社にとって適切な評価指標を選ぶことも必要なのです。
これからの中小企業には、「新しいことをやる」だけでなく、自分たちに合ったやり方や評価のしかたを考えながら、イノベーションを続けていく力が求められます。
イノベーションは、決して万能の魔法ではありません。しかし、自社の状況やリソース、文化に合ったアプローチを見極め、地に足のついた取り組みを重ねていくことで、確かな競争優位へとつながる道は確かに存在しています。
参考文献:Nina Rosenbusch, Jan Brinckmann, Andreas Bausch. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs.