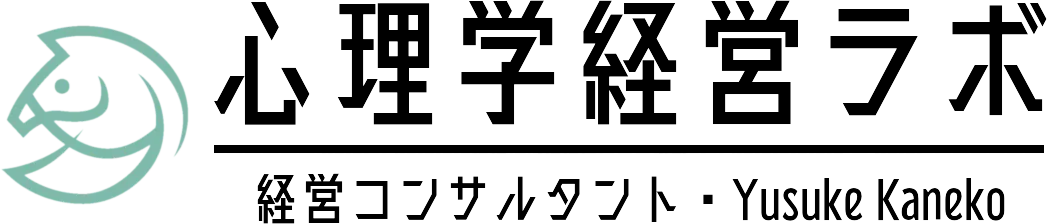リーダーの資質というと、指導力やカリスマ性といったものが思い浮かびますが、そのようなものを持っているリーダーはそれほど多くありません。
リーダー自身がそのことを自覚していたりします。
経営者から見ても、「うちの管理職はちょっと勢いが足りないな」なんて思ったりするかもしれません。
しかし、リーダーに必要なのは、そうした「いかにもリーダー」といった資質に限りません。
誰でも持つことのできる「謙虚さ」も、リーダーにとって必要なものなのです。むしろこれからの時代はリーダーの謙虚さこそが、組織の強さを決める要因といえます。
謙虚なリーダーが率いる組織は、業績も良くなるのです。
リーダーが持つべき「謙虚さ」とは
ここでいうリーダーの「謙虚さ」とは、ただ控えめだったり遠慮がちだったりすることではありません。
職場という社会的な場面において発揮される、対人関係に根ざしたものです。大まかに以下の三つの要素で説明できます。
一つ目は、自分のことを正しく見つめる力です。たとえば、自分の得意なことや苦手なことをきちんと理解し、間違いや失敗があったときには素直に認めることができる姿勢です。こうしたリーダーは、無理に自分を大きく見せたりせず、ありのままの自分を見せることができます。
二つ目は、周りの人の力をきちんと認めて、感謝できることです。部下やチームメンバーがどんな貢献をしたかをしっかり見ていて、それを言葉や行動で伝えることができるリーダーは、周囲からの信頼を集めやすくなります。
三つ目は、新しい考えや他人からのアドバイスに対して、素直に耳を傾ける姿勢です。たとえ部下であっても、そこから学ぼうとする気持ちを持っているリーダーは、チームの中にオープンで前向きな雰囲気をつくり出すことができます。
このように、謙虚なリーダーとは、周囲との関係の中で、自分を客観的に見つめ、人の力を認め、学ぼうとする姿勢を持っている人のことを指しています。リーダーのこうした姿勢が、チームの心理的安全性や前向きさにつながり、最終的にはチーム全体のパフォーマンスを高めるのです。
リーダーの謙虚さとチームのパフォーマンスの関係
リーダーの謙虚さがどのようにチームの成果へとつながるかを調べた、カトリカ・ポルトビジネススクールのアルメニオ・レゴ教授らの調査があります。
人事、研究開発、営業など、幅広い職種を対象としたものです。
この調査ではまず、チームのメンバーがリーダーの謙虚さについて評価しました。
評価項目は先ほど説明した3つの要素です。リーダーが自分の限界を認めるか、他者の強みに感謝するか、新しい意見に対して開かれているか、といったことです。
次に、そのチームのパフォーマンスを確認しました。
仕事を効率的にこなしているか、高い業績を上げているか、目標を達成しているかといったことを確認しました。
その結果、リーダーの謙虚さとチームのパフォーマンスには相関があることが分かりました。
謙虚なリーダーがいるチームほどパフォーマンスが高かったのです。
【関連】サーヴァントリーダーシップが飲食店の人手不足を救う!離職率の低下は店長のスタイル次第
リーダーが作る「心理的資本」
なぜリーダーの謙虚さが業績に影響するのでしょうか?
それはチーム全体の心理的な状態と協働の質に良い影響を与えるためです。
謙虚なリーダーは、自分の限界や過ちを率直に認め、他者の強みや貢献に敬意を示します。また、部下からの提案やフィードバックに耳を傾け、学ぼうとする姿勢を持っています。
こうした行動は、「誰でも完璧である必要はない」という安心感をチームにもたらし、メンバーが自分の意見を自由に表現しやすい心理的な安全性を高めます。
その結果、チーム内には希望や自信、回復力、そして未来に対する前向きな期待が育まれます。こうしたポジティブな心理状態は「心理的資本」と呼ばれ、チームの感情的な土台として重要な役割を果たします。今回の調査でもリーダーの謙虚さがチームの心理的資本を高めることが分かっています。
心理的資本が高まることで、メンバーは自分や他のメンバーの強みに対する理解を深め、自然とそれぞれの能力に合った仕事の分担が行われるようになります。つまり、チーム全体で「誰が何を得意としているか」を把握し、それに応じた役割配分ができるようになるのです。
適切なタスク配分が実現すると、メンバーは自身の能力を最大限に発揮しやすくなり、無理や無駄の少ない効率的なチーム運営が可能になります。
さらに、メンバー同士の信頼や協力も深まり、困難な課題にも柔軟かつ粘り強く取り組む姿勢が育ちます。このような一連のプロセスを通じて、謙虚なリーダーの存在はチームの内面を整え、結果としてパフォーマンスの向上を導くのです。
つまり、リーダーの謙虚さは、直接的に指示や命令で成果を引き出すのではなく、チームが自律的に機能しやすい環境をつくることで、内側から力を引き出し、チーム全体の能力と連携を高める働きをしているということです。
次世代のリーダーをどう選ぶか?
今回の調査からも分かるように、リーダーに求められるのは実行力やカリスマ性だけではありません。
チームメンバーの強みを引き出し、心理的な土台を整え、組織全体をしなやかに動かす「謙虚さ」なのです。
変化の激しい時代においては、トップダウン型の強いリーダーシップよりも、現場の声に耳を傾け、対話を通じて方向性を定めていく柔軟な姿勢が求められます。
さらに、謙虚なリーダーには、部下の成長に焦点を当てる傾向があることが他の研究でも報告されています。
こうしたリーダーのもとでは、若手が自分の潜在能力を発揮しやすくなり、組織全体の人材育成にもつながります。
つまり、謙虚さは「成果を出すための手段」であると同時に、「人を育て、組織を強くする力」でもあるのです。
経営者として次世代のリーダーを選ぶ際には、他者の意見に耳を傾けられるか、自分の限界を認められるか、そして周囲の成長を心から支援しようとする姿勢があるかを見極めることが重要です。
参考文献:Rego, A., Owens, B., Yam, K. C., Bluhm, D., Cunha, M. P. e, Silard, A., Gonçalves, L., Martins, M., Simpson, A. V., & Liu, W. (2017). Leader Humility and Team Performance: Exploring the Mediating Mechanisms of Team PsyCap and Task Allocation Effectiveness.