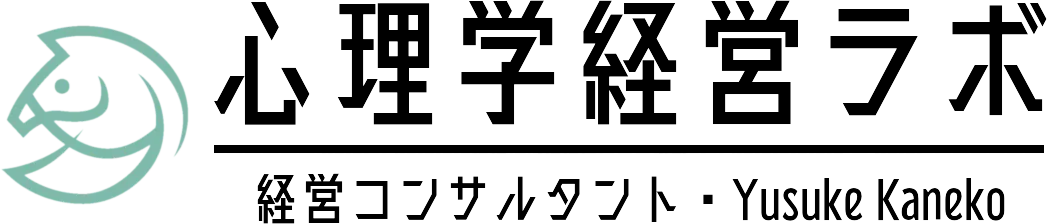ナレッジシェアとは、職場などの組織内で、個人が持っている知識や経験を他の人と共有することです。
たとえば、ある業務でうまくいった方法や、特定のソフトの使い方、過去に失敗したときの教訓などを、同僚に伝えるような行動が該当します。
こうした、マニュアルに書かれていない「現場の知恵」を社内に広げることで、仕事の質や効率を高めることができます。問題の早期解決やイノベーションの促進にもつながります。
ただし、ナレッジシェアは自発的な行動であるため、知識を「自分だけのもの」にしてしまう社員も少なくありません。
では、どうすれば自然とナレッジシェアが広まる職場を作ることができるのでしょうか?
一つの答えは、リーダーが部下を尊重する態度を持つことです。
社会的マインドフルネスとは
そもそも、なぜ社員はナレッジシェアをしようと思うのでしょうか?
それは、「この情報を共有すれば、同僚の役に立つかもしれない」という、思いやりの気持ちがあるからです。
このような他者志向の態度を「社会的マインドフルネス」と呼びます。
社会的マインドフルネスには、二つの要素があります。
一つは「視点取得」と呼ばれるもので、相手の立場や状況を頭の中で想像する力です。
もう一つは「共感的配慮」といい、相手がどんな感情を抱いているのかを感じ取り、それに共鳴する感情的な働きです。
これらは、生まれ持った性格による部分もありますが、職場環境の影響も受けます。
「この職場の仲間の役に立ちたい」と思えるような環境の有無によって、社員が社会的マインドフルネスを持てるかどうかは変わります。
そして、それにはリーダーの態度が影響するのです。
リーダーが「尊重の心」をもって接すれば、社員の中にこのような社会的マインドフルネスの感覚が芽生え、結果的にナレッジシェアが広まります。
【関連】中小企業が知識吸収能力(アブソープティブ・キャパシティ)を高めるために必要なもの
上司の尊重的態度→社会的マインドフルネス→ナレッジシェア
リーダーの尊重的態度とナレッジシェアの関連について検証した、WHUオットー・バイスハイム経営大学のファビオラ・ガーポット教授らによる調査があります。
この調査では、まず実在の会社の社員にアンケートを行い、上司が自分に対してどれくらい尊重的な態度を取っているかを聞き取りました。アンケートには「上司は私と私の仕事を真剣に扱っている」などの項目が並んでいました。
それから一週間後、今度は社員本人が、どの程度「社会的マインドフルネス」を持っているかを測定しました。ここでは、先ほど説明した2点を評価しています。
- 視点取得:質問例「意見が異なるときでも、相手の立場に立って考えようとする」
- 共感的配慮:質問例「困っている人を見ると放っておけない」
さらにその1週間後、3回目のアンケートを行い、実際に職場でどれくらいナレッジシェアしているかを尋ねました。
この段階では、同僚に対して業務上のノウハウや手順を教えているかどうか、自分の経験やスキルを周囲に伝えているかといった具体的な行動に注目しています。
「自分が知っている効率的な方法を、同僚に進んで教えることがあるか?」といった設問を用いて、実際の行動レベルでの知識共有を把握したのです。
その結果、上司が尊重的であればあるほど、部下の視点取得や共感的配慮のレベルが高くなり、ナレッジシェアも進むことが明らかになりました。
また、別の企業を対象とした調査では、ナレッジシェアの程度を本人ではなく、上司に聞き取りました。こちらでも、上司の態度が尊重的であるほど、部下が他の同僚に対して、積極的にナレッジシェアをする傾向が見て取れました。
なぜリーダーの尊重的な態度がナレッジシェアを促進する理由
なぜ、リーダーが尊重をもって接することで、社会的マインドフルネスを高め、ナレッジシェアを促進するのでしょうか?
それは人間が他者からの扱われ方によって、考え方や行動を調整するという、心理的な特性を持っているからです。
1.自分が大切にされると、他人を大切にする
リーダーが部下を価値ある存在と認め、その考えや感情を真剣に受け止める態度で接すると、部下は自分が大切にされているという実感を得るようになります。
この実感は、他者に対する意識のあり方にも影響を及ぼし、今度は「自分も他者を尊重しよう」という気持ちが生まれるのです。
その結果、ナレッジシェアも増えるということです。
2.無意識に行われる社会的学習
また、リーダーは組織内で模範として見られる存在でもあります。
部下は、日々の業務の中でリーダーの振る舞いを観察しており、その言動を無意識のうちに模倣する傾向があります。
リーダーが周囲の意見に耳を傾け、感情に配慮した接し方を実践していれば、部下もそのような態度を「望ましい行動」と認識し、行動に取り入れるのです。
心理学でいうところの「社会的学習」が無意識のうちに行われているということです。
3.心理的安全性からくる他者を配慮する余裕
さらに、自分が尊重される経験を通じて得られる心理的安全性も、社会的マインドフルネスの土台となります。
人間は安心できる環境に身を置いてはじめて、他者に注意を向けたり、他人のために行動したりする余裕が生まれます。逆に、自分が軽んじられていると感じているときには、周囲への配慮や共感は後回しになりがちです。
このように、尊重的なリーダーシップは、部下の内面的な動機づけに働きかけ、他者を思いやる姿勢を引き出します。
それによって、視点取得と共感的配慮という社会的マインドフルネスの2つの要素が高まり、より協力的で思いやりのある職場環境が形成されていくのです。
ナレッジシェアを促進するための対策
ナレッジシェアを促進するために企業が取るべき対策は、職場内の人間関係、特にリーダーと部下の関係の「質」を高めることです。
情報共有ツールを導入したり、インセンティブを設けたりするだけでは、社員が自発的に知識を提供しようとはしません。
知識の共有が自然に起こるためには、職場における心理的な土壌が整っていることが重要なのです。
まずはリーダーシップの質を高めましょう。たとえば、管理職の選抜にあたっては、部下に対する態度や人間性を評価基準に加えることが重要です。
また、リーダーシップ研修では、尊重の具体的な示し方(意見に耳を傾ける姿勢、信頼を前提とした対話、相手の価値を認める表現など)を中心に据えてください。これにより、リーダーは部下との関係性を深め、信頼と安心のある職場環境を築くことができます。
社員一人ひとりの社会的マインドフルネスを高める取り組みも有効です。視点取得を養うワークショップや、共感をテーマにした対話の場を設けることは、他者への関心を高めるきっかけになります。
ナレッジシェアを特別な成果として評価するのではなく、組織文化として根づかせることも大切です。知識を共有することが信頼や協力の一部と見なされるような価値観を明確に打ち出し、日常的に賞賛や感謝を伝え合う文化を育てていく必要があります。
こうした文化が醸成されることで、ナレッジシェアが「評価のための行動」ではなく、「組織の一員として当然の貢献」として認識されるようになるのです。
参考文献:Gerpott, F. H., Fasbender, U., & Burmeister, A. (2019). Respectful leadership and followers’ knowledge sharing: A social mindfulness lens.