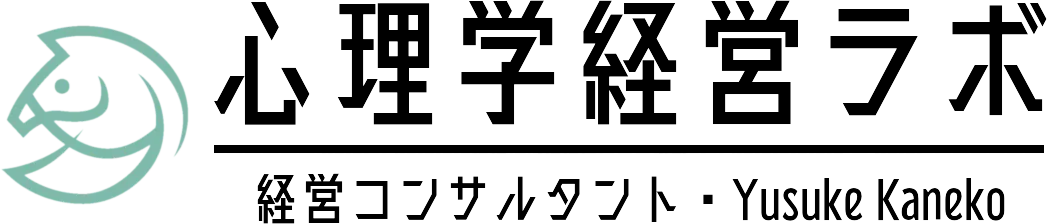異常なほど早いテクノロジーの進化によって、市場環境が目まぐるしく変化する時代となっています。
そのため、いつまでも従来の仕事のやり方を続けている企業は、あっという間に淘汰されてしまいます。
しかし、組織を変革しようとしても、従業員が抵抗を示すものです。
そんなとき、どうすれば従業員に変革を受け入れてもらえるのでしょうか?
それは、変革を「今までの延長線上にあるもの」として伝えることです。
これによって人間の持つ「現状維持バイアス」を抑制できるのです。
現状維持バイアスとは
現状維持バイアスとは、人間が「今の状態を変えずにそのままにしておきたい」と感じ、変化を避ける傾向のことです。
これは保守的な性格によるものではなく、多くの人に共通して見られる心理的メカニズムです。
この背景にはいくつかの要因があります。
まず、変化には必ず不確実性やリスクが伴います。新しい方法が本当に良いのかどうかは試してみないと分からないため、人は「失敗するかもしれない」という不安を強く意識します。
その一方で、現状を続けることには安心感があり、「少なくとも今のままであれば大きな損はしないだろう」と考えやすいのです。これが、変化に対して抵抗を感じる一因です。
また、認知の仕組みも影響しています。人はすでに慣れた選択肢や行動パターンを「標準」として捉えるため、それを変えることに強いストレスを感じるのです。
この現象は、個人の買い物や生活習慣の選択にとどまらず、組織や社会の意思決定にも影響します。
例えば、企業で新しい制度や技術を導入しようとしても、従業員が「今のやり方で十分だ」と感じて受け入れにくいのは現状維持バイアスが働いているからです。
現状維持バイアスの悪影響を排除するには
では、組織変革を進める際に現状維持バイアスの悪影響を排除するにはどうすれば良いのでしょうか?
それは変革を「全く新しいもの」ではなく「今までの延長線上にあるもの」と位置づけることです。
「新しい仕組みや方法を導入する」と強調するよりも、従来のやり方とのつながりを明確に示しつつ「これまでの方法を大きく変えるわけではない」という安心感を与えるのです。
従業員は自分が慣れ親しんできた手順や環境に強い親近感を抱いており、それが崩れると心理的な負担を感じやすくなります。そのため「全く新しいもの」として提示すると、不確実性やリスクに対する警戒心が高まり、反発や抵抗が強まってしまうのです。
一方で、「今までの仕組みを基本的に引き継ぎつつ、一部が改善される」と伝えれば、従業員は自分の経験やスキルが引き続き役立つと理解でき、不安を感じにくくなります。
さらに、その改善点が具体的で理解しやすいものであれば、「従来の延長線上で、便利さや効率が少し高まる」という前向きな期待を持ちやすくなるのです。
実験結果
変革を今までの延長線上にあるものと位置づけることで、現状維持バイアスの悪影響を抑えられることはサザンクイーンズランド大学の研究チームによる実験でも明らかになっています。
どんな伝え方が受け入れられやすいのか
この実験では今までのやり方や環境を変えるときに、どのような伝え方をすると受け入れられやすいかを調べています。
例えば、経理の支払い処理を完全にオンライン化する際に、次のどちらが受け入れやすいかということです。
- 現在使用しているものと大きく異なり、数日間の集中トレーニングが必要
- 現在使用しているものと非常に似ており、数日間の集中トレーニングが必要
前者は新規性をアピールし、後者は今までの延長線上にあることをアピールしています。
実験参加者の回答を分析したところ、後者のほうが受け入れられやすいことが分かりました。
現状維持バイアスとリスク回避志向が相互に作用
なぜこのような結果となったのでしょうか?
ここまで説明した通り、人間は新しい選択肢よりも慣れ親しんだ選択肢を好む「現状維持バイアス」に強く影響されます。
特に業務システムのように日常的かつ反復的に使用するものについては、学習コストや適応にかかる負担を避けたいという心理が働きます。
実験の選択肢では両システムとも数日間のトレーニングが必要とされていましたが、後者の選択肢では「現状と似ている」という特徴が安心感を与え、学習が容易に感じられたのです。
また、リスク回避傾向も影響しています。人間は不確実性を嫌うため、全く新しいシステムよりも、既存に近いシステムの方が導入後の失敗や不便が少ないだろうと直感的に判断します。
特に「経理部門での支払い処理」という文脈では、業務の正確性や継続性が重要視されるため、リスクを最小化する選択が強く支持されやすいのです。
こうした現状維持バイアスとリスク回避志向が相互に作用し、現状に近い選択肢を強く好んだということです。
【関連】イノベーションが成功する中小企業の特徴。21,270社のデータから分かった条件
組織変革を成功させる具体策
企業が現状維持バイアスの悪影響を排除して組織変革を成功させるためには、従業員の「変わることで損をするのではないか」という不安を和らげることが必要です。
現状維持バイアスは、変化を脅威として捉える心理から生じるため、過去の方法を否定しようとすると抵抗が強まります。したがって、変革を推進する際には「これまでの取り組みや経験が大切にされている」という感覚を従業員に持たせることが重要なのです。
具体的には、変革の内容を「これまでと大きく異なるもの」ではなく「今のやり方を土台にした自然な延長線上の取り組み」として伝えることが効果的です。
例えば、「操作方法はこれまで通りだが、より効率的になる」「チーム構成は維持したまま、新しいツールが追加される」といった説明は、安心感を与え、抵抗を最小限に抑えます。
また、改善点を小さく区切り、段階的に導入することで負担を軽減し、少しずつ新しい環境に慣れてもらう方法も有効です。
さらに、従業員に変革の理由を具体的かつ納得感のある形で伝えることも大切です。
「市場競争で勝ち残るため」といった抽象的な説明ではなく、「日常業務が効率化される」「顧客対応が迅速になる」といった身近な利益を強調することで、変革が自分にとって意味のあるものであると理解しやすくなります。
変革をただ上から押し付けるのではなく、従業員自身を巻き込み、意見を取り入れながら進めることが成功の要諦です。当事者意識を持つことで「自分が関わっている変化である」と感じられ、現状維持への固執が弱まります。
このように、現状維持バイアスを理解したうえで「継続性」「具体的なメリット」「従業員の主体性」を組み合わせ、変革に伴う抵抗を減らすことで、組織変革を成功に導くことができます。
参考文献:Tom A.S. McLaren, Erich C. Fein, Michael Ireland, Aastha Malhotra; I’ll have what I had before, but with a cherry on top: leveraging status quo bias when introducing organizational change. Journal of Organizational Change Management 12 December 2025; 38 (8): 50–70.