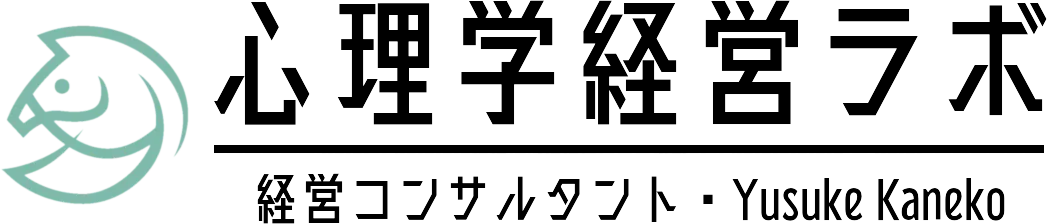多くの中小企業が直面する課題のひとつが、「リソースの限界」です。
限られた人材、限られた時間、限られた予算──。
この制約の中で成果を出すためには、外部リソースの活用、つまりアウトソーシングが非常に有効な手段となります。
しかし、ただ外注するすだけでは、期待した成果は得られません。
大切なことは、「戦略的アウトソーシングを行っているかどうか」です。
800社以上を対象とした調査では、単に外注しているだけの企業よりも、戦略的アウトソーシングを行っている企業のほうが、コスト削減効果が高く、サービス品質も高まりやすいことが分かっています。
戦略的アウトソーシングとは
戦略的アウトソーシングとは、企業が自社の経営戦略に基づいて、特定の業務や機能を外部の専門業者に委託することです。
単なる経費削減や、人員不足解消を目的とした外注とは異なり、長期的な競争優位の確立や企業のコア業務への集中を目指して行われます。
たとえば、情報システムの運用や人事業務、物流、カスタマーサポートなど、企業にとって重要ではあるものの、必ずしも自社内で行う必要がない業務について、外部の高い専門性を持つ企業に任せることで、より効率的かつ柔軟な経営が可能になります。
このような戦略的アウトソーシングは、コストの最適化に加えて、品質向上や市場変化への迅速な対応、最新技術の活用など、さまざまな戦略的メリットをもたらします。
戦略的アウトソーシングの効果
中小企業が外注(アウトソーシング)をどのように使っているのかを調べた、アイスランド大学のインギ・エドヴァルドソン教授らの研究があります。
この研究では、従業員が5人以上の企業802社を対象にアンケート調査を行っています。
質問内容は、「どんな業務を外注していますか?」「外注するための計画は立てていますか?」「外注する理由は何ですか?」「業者はどうやって選びましたか?」など、企業が外注についてどう考えているのか、どんなやり方をしているのかを詳しく聞くものでした。
また、「会社の規模」「業種」「社長の学歴や年齢」などの情報も集めて、会社ごとの違いがどう影響しているかも見ています。
さらに、コスト削減や、サービス品質の向上などの効果があったかも確認しています。
調査は1回だけではなく、2009年、2013年、2018年の3回にわたって行われ、そのデータをまとめて分析しています。こうすることで、10年間の変化も確認できるようにしています。
収集した回答を、専門のソフトを使って分析し、「戦略を立てて外注している会社」と「なんとなく外注している会社」とでは、成果や考え方に違いがあるのかを比べました。
戦略がある企業は、やはり成果が違う
調査結果からまず明らかになったのは、中小企業の多くがすでにアウトソーシングを活用しているという事実です。
実際、全体の約80%もの企業が、過去3年以内に何らかの業務を外部に委託していたと回答しています。
しかし、ここで重要なのは「戦略的に」アウトソーシングしている企業は、わずか23.5%しかなかったという点です。
つまり、残りの企業の多くは、明確な方針や計画を持たずに、場当たり的に業務を外に出しているということです。
では、戦略の有無でどのような違いが生まれるのでしょうか?
結論からいうと、戦略的なアウトソーシングを実施している企業の方が、明らかに多くの成果を得ていることが分かりました。
具体的には、以下のような点で優れた効果が確認されています。
- コスト削減の達成度が高い(特に財務管理の費用など、固定費に対する効果が顕著)
- サービスの質が向上
- 自社のコア業務に集中できる環境が整った
とくに注目したいのは、「コア業務への集中」という点です。
戦略的にアウトソーシングを行っている企業では、会計業務や清掃、ITサポート、警備など、自社にとって「コアではない」業務を意図的に外部へ委託しています。
こうした選択によって、社内のリソース(人員・時間・資金)を、本当に注力すべき事業や価値創出に向けることが可能になっているのです。
一方で、戦略を持たずにアウトソーシングしている企業では、「なんとなくコストを抑えられそうだから」「社内でできる人がいないから」といった、短期的・反応的な理由で業務委託を行っているケースが多く、結果として得られる効果に差が出てしまっているのです。
ベンダーの選び方にも「戦略性」が表れる
さらに面白いのは、委託先(ベンダー)の選定基準にも、明確な差があったという点です。
戦略的なアウトソーシングを行っている企業は、ベンダーを選ぶ際に「コストパフォーマンス」や「提供されるサービスの質」といった合理的かつ客観的な指標を重視しています。つまり、ビジネスパートナーとして冷静に選び抜いているのです。
対照的に、戦略のない企業では「知人の紹介だから安心」「昔からの付き合いがあるから」といった、人間関係や慣習に依存した選定をする傾向が強く見られました。
この違いは、当然ながらアウトソーシングの成果にも直結します。
仮に価格が安くても、期待したサービスが提供されなければ、そのアウトソーシングは失敗です。
逆に、多少コストがかかっても高品質なアウトプットを継続的に受けられるパートナーを選べば、企業全体の競争力は確実に高まっていきます。
信頼関係はもちろん大切ですが、コスト削減や品質向上といった具体的な成果を追求するなら、定量的な評価軸でパートナーを選ぶ姿勢が不可欠なのです。
外注先は「学びの場」にもなる
もうひとつ特筆すべき点があります。それは、戦略的アウトソーシングが単なる「業務の外注」にとどまらず、企業にとっての学習の機会にもなっている、ということです。
外部の専門家やプロフェッショナルと業務を通じて連携することで、最新の知識やスキル、業界のベストプラクティスを吸収する機会が自然と生まれます。
中には、社内に存在しなかったノウハウや発想を、外部との協働によって獲得している企業もありました。
このように、アウトソーシングはただのコスト削減の手段にとどまりません。外部の力を活用しながら、自社の弱点を補強し、将来的には自走できる組織へと進化させるための学習プロセスとしても機能するのです。
中小企業が戦略的アウトソーシングをするためのポイント
以上のように、中小企業が持続的な成長を目指す上で、業務の一部を外部に委ねるアウトソーシングは有効な選択肢となりえます。
ただし、成果を上げるには場当たり的な外注ではなく、戦略的な判断が不可欠です。
以下では、アウトソーシングを効果的に活用するための実践的なポイントを整理します。
1.自社の業務を「コア業務」と「ノンコア業務」に分ける
はじめに行うべきは、会社内のすべての業務を棚卸しし、それぞれが「コア(中核)業務」か「ノンコア(補助)業務」かを見極めることです。
コア業務とは、企業の競争力の源泉となる活動であり、自社ならではの強みや顧客価値に直結する業務のことです。たとえば、IT企業であればソフトウェア開発、飲食店であればメニュー開発や接客などがこれにあたります。
一方、ノンコア業務は、会社の価値提供に直接関与しないものの、日々の運営には欠かせない業務です。経理、人事、清掃、警備、ITサポートなどが代表例です。
この分類を行うことで、外部に委託すべき業務の候補が自然と見えてきます。
2.ノンコア業務のうち、外注可能なものを明確な基準で選ぶ
ノンコア業務のすべてが必ずしもアウトソーシングに適しているとは限りません。そこで重要になるのが「委託可能性」を判断するための基準を設けることです。
たとえば、以下のような視点が有効です。
- 業務の標準化・明文化ができているか
- 外部に任せても情報漏洩などのリスクがないか
- 外部業者の専門性が自社より高いか
- 委託によってコスト削減や品質向上が期待できるか
これらの基準をもとに、何を委託するのか、そして何を社内に残すべきなのかを、冷静に判断する必要があります。
3.ベンダーは「実績」と「サービス品質」で選ぶ
多くの中小企業では、ベンダー選定を「知人の紹介」や「人間関係」で決めてしまう傾向があります。
しかし、今回の研究では、戦略的に成功している企業ほど、コストやサービス品質といった客観的な指標を重視していることがわかりました。
それを踏まえると、ベンダー選びでは、以下の観点が大切です。
- 過去の実績や取引先の評価
- 専門性や技術力の明確な証拠(資格・導入事例など)
- 提供するサービスの内容と範囲、対応スピード
- 契約やサービスレベル基準が明確かどうか
信頼関係は重要ですが、それに頼りすぎず、第三者的な目線で選定することが成果を左右します。
4.契約後も「学び」と「連携」を意識する
アウトソーシングは「外に任せたら終わり」ではありません。むしろ、契約後のマネジメントとパートナーシップの築き方が重要です。
優れたベンダーとの協働を通じて、業務の進め方や新しい技術、業界の動向など、さまざまな知見を得ることができます。
このような「外からの学び」を社内に還元していくことで、組織全体の知的資産が増えていきます。
また、定期的な打ち合わせやレビューを行い、パフォーマンスの確認や改善点の共有を図ることで、より安定した協力関係が築かれます。
外部とつながりながら組織を強くするという姿勢が大事
今回の研究では従業員の学歴との関連性にも触れられており、従業員の半数以上が大学教育を受けている企業ほど、アウトソーシング戦略を持つ傾向があることが明らかになっています。
これは、高度な教育を受けた人材ほど、より計画的かつ戦略的な意思決定を行う傾向にあるからです。
つまり、組織の人的資源の質が、アウトソーシングの「質」にも影響しているのです。
戦略的アウトソーシングは、単なる業務効率化にとどまらず、経営そのものの質を高める手段になり得ます。
リソースの最適配分、専門性の獲得、学習の加速──それらを実現する鍵は「戦略性」にあります。
中小企業にとって、「すべてを自前で賄う」時代はすでに過去のものです。
外部とつながりながら、賢く学び、強くなるという姿勢が、これからの経営には求められているのです。
参考文献:Ingi Runar Edvardsson, Susanne Durst, et al. (2019). Strategic outsourcing in SMEs.