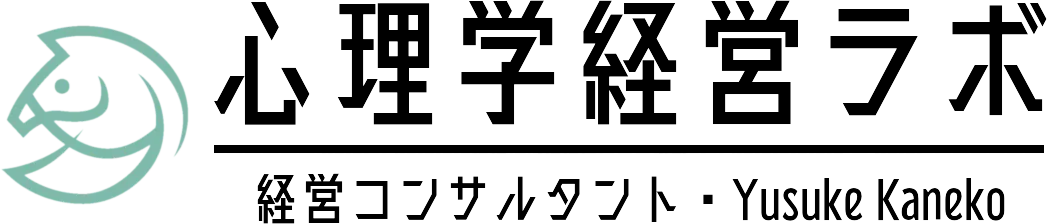せっかく優秀な人材を採用したのに、すぐに辞めてしまった…、という経験は多くの経営者が持つものです。
特に中小企業やスタートアップでは、スキルの高い人材を確保すること自体が難しいにもかかわらず、その貴重な人材が短期間で離職してしまうケースが後を絶ちません。
では、なぜ優秀な社員ほどすぐに辞めてしまうのでしょうか?
その背景には、「オーバークオリフィケーション」という、見落とされがちな要因が潜んでいるかもしれません。
オーバークオリフィケーションとは
オーバークオリフィケーションとは、その社員が保有している知識、スキル、経験、学歴などが、現在任されている仕事の要求水準を大きく上回っている状態のことです。
必要以上に過剰(over)な、資格・能力(qualification)を持っているということです。
たとえば、高度な専門知識やマネジメント経験を持つ人が、単純作業やルーチンワークを日々繰り返しているようなケースがこれに該当します。
このような状態になると、仕事に対して「本来の自分の能力を活かせていない」「この仕事は自分でなくてもできるのではないか」といった感情が芽生えやすくなります。
特に、自己成長や達成感を重視する人にとっては、仕事と能力のミスマッチが強い心理的ストレスの原因になります。
実際の職務内容と自分の能力・期待との間に大きなギャップがあると、それを長期間受け入れることは難しくなり、次第に「この職場ではもう学べることがない」「ここで時間を無駄にしてはいけない」と感じるようになるのです。
このように、オーバークオリフィケーションは単なる「ぜいたくな悩み」ではなく、本人のキャリア満足度や職場定着率に深く影響する重要な要因といえます。
優秀な人ほど辞めていくという研究結果
ソウル大学とフロリダ大学の研究者たちが2024年に発表した、オーバークオリフィケーションと離職に関する研究があります。
この研究では、全国調査のデータを使って、3年間に渡り、企業で働く人たちの変化を追いかけました。それぞれの年度ごとに以下のことを確認しています。
- 1年目:仕事の内容と自分のスキルが合っていると思うか?
- 2年目:仕事の中で自分が成長できていると感じているか?
- 3年目:その会社に今も在籍中か、それとも辞めたか?
また、その影響が「年齢」や「給料」によって変わるかどうかも確認しています。
研究の結果、自分のスキルが今の仕事に対して過剰すぎると感じている人(=オーバークオリフィケーションを認識している人)は、「この仕事では成長できない」と感じやすいことが分かりました。
そして、「成長できない」と感じている人は、実際に会社を辞める可能性が高いという結果になりました。
つまり、「スキルが余っている→成長できないと感じる→会社を辞める」という流れが存在しているということです。
給料を上げれば引き留められるか?
経営者の中には「オーバークオリフィケーションを感じている社員の給料をアップすれば辞めないのでは?」と考える人もいるでしょう。
研究では、年齢の高い社員であれば、その効果が期待できることが分かっています。
年齢が高く、ある程度キャリアを積んだ社員は、「もう成長より安定が大事」という価値観にシフトしているため、高い給料が離職の抑止力として機能しやすいのです。
しかし、優秀な若手社員には、給料アップの効果はあまり期待できないことも判明しています。
若手社員は「成長」の価値をより重視するからです。どれだけ給料が良くても、日々の仕事に挑戦や刺激がなければ、すぐに見切りをつけてしまうのです。
企業ができることは何か?
では、企業はどのような取り組みを行えば、優秀な人材を長期的に活かし、離職を防ぐことができるのでしょうか。研究をふまえると、以下のような工夫が有効だと考えられます。
1.スキルに応じたチャレンジングな業務を任せる
社員の持つスキルや経験に見合った、難易度の高い業務や責任あるプロジェクトを意識的に割り当てることが重要です。「この仕事は自分にしかできない」「少し背伸びが必要だけれど挑戦してみたい」と感じる機会が、仕事への意欲と満足感につながります。
2.定期的な異動や職務拡大の検討
同じ職務に長くとどまっていると、成長の実感は得られにくくなります。そのため、部署異動やプロジェクト配属などによって、新しい環境や業務に触れる機会を提供することが効果的です。また、現在の職務に追加的な責任や裁量を与えることで、役割の幅を広げることも一つの方法です。
3.社内外での学習機会や研修の提供
自己成長を重視する人材にとって、学びの機会は非常に魅力的です。職務に直結したスキル研修はもちろん、業務外の知識やリスキリングの支援、外部セミナーや資格取得の補助制度なども、学習意欲を刺激し、モチベーションの維持につながります。
4.キャリアパスについて個別に話し合う
社員一人ひとりが「この会社でどのように成長していけるか」を具体的にイメージできるように、定期的な面談やキャリア面談の機会を設けることも有効です。漠然とした将来像ではなく、「3年後にはこういうポジションを目指せる」「この経験が次のキャリアに活きる」といった具体的な道筋を示すことが、成長意欲を高めます。
オーバークオリフィケーションの問題は他の社員にも波及する
オーバークオリフィケーションの影響は職場内の人間関係にも波及することがあります。
優秀すぎる社員は、自分のスキルが活かされないだけでなく、同僚や上司との関係性にも違和感を覚えやすくなることが報告されています。
たとえば、自分の意見が軽視されたり、業務の改善提案が受け入れられないといった状況に直面すると、「この職場では本当の意味で貢献できない」と感じやすくなるのです。
また、周囲の社員がその人のスキルの高さに引け目を感じたり、距離を取ってしまうようなケースもあります。これにより、本人の「職場への一体感」や「所属意識」が低下し、さらに離職リスクが高まるという悪循環が生まれます。
つまり、オーバークオリフィケーションの問題は単なるスキルと業務内容のミスマッチにとどまらず、職場のコミュニケーションやチームの健全性にも関わってくるのです。そのため、企業が取るべき対策は人事制度や業務設計にとどまらず、組織文化や対話のあり方にも踏み込む必要があります。
「この職場では自分の存在が歓迎されている」「自分の力が正しく評価され、活かされている」という感覚が得られる職場づくりこそが、優秀な人材を惹きつけ、留めておくための最も強力な土台となるのです。
参考文献:Mah, S., Huang, C. & Yun, S. Overqualified Employees’ Actual Turnover: The Role of Growth Dissatisfaction and the Contextual Effects of Age and Pay.